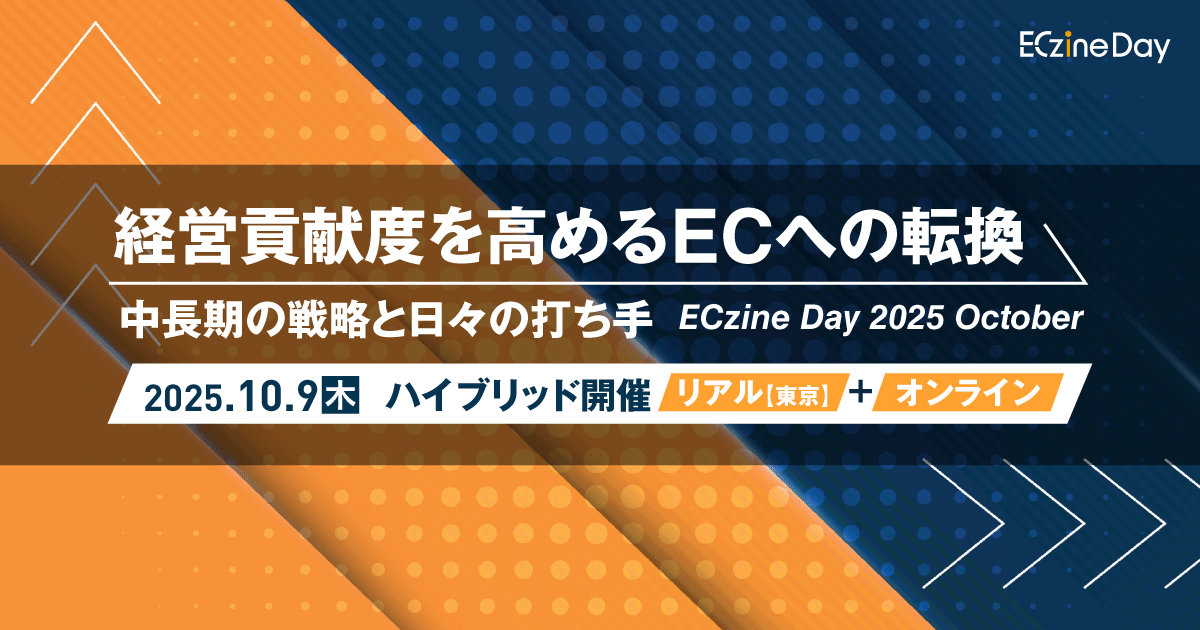変わるレビューの形 「誰が」「何について」評価しているかが重要に
ECサイトにおけるUGC(ユーザー生成コンテンツ)の活用が増えている。その代表とも言えるのが「レビュー」だ。ZETAの調査によれば、ECにおける売上トップ100にランクインするサイトのレビュー機能導入率は75%。ここ数年で、導入数とともにレビューの機能自体も進化してきた。
「当初は商品に対する総合評価をスターレーティング(星の数)で表示するサイトが多かったのですが、今日では複数の評価項目を設けた多軸レビュー、レビュアーの属性を示すレビュアー情報の掲載、画像投稿機能など多機能化が進んでいます」(山崎氏)

レビュー機能が拡充される中でとくに重要なのは、レビュアー情報と多軸レビューだと山崎氏は言う。
「『どんな人が』『何について』評価しているのかわからなければ、ユーザーはその商品が自分に合うかどうかを判断できません。レビュアー属性と評価項目の掛け合わせでデータが増えるとともに精度が高まり、より多くのユーザーに有用な情報を提供できるようになります」(山崎氏)

自分以外のユーザーから寄せられたレビューは購入判断の参考になり、それがポジティブな評価であればソーシャルプルーフとなり得る。山崎氏は「レビューはブランドやメーカーからの説明より12倍信頼されているという調査データもある」と付け加えた。
レビューを発展させ、双方向性を持たせたUGCが「Q&A」だ。購入を検討しているユーザーが商品について質問を投げかけ、該当商品の購入者や店舗スタッフ、ときにはECのスタッフやメーカーの担当者が回答する。そこから質問や回答が複数続くケースもある。複数人のコミュニケーションから生成されるという意味では、よりSNSに近いUGCだ。
「Q&Aに参加するユーザーの多くは購入に対して前向きで、ほかのユーザーによる評価を求める傾向も強いです。そのためQ&Aは非常に影響力の大きいUGCと言えます」(山崎氏)
レビューやQ&Aに加え、最近ではTwitterなどのSNSでおなじみの「ハッシュタグ」もECサイトで活用されるようになってきた。商品説明の下に複数のハッシュタグを付け、それらをクリック(タップ)すると同じハッシュタグに紐づく商品やレビューの一覧が表示されるというものだ。

「ハッシュタグは、『ある商品から別の商品』『商品からレビュー』『レビューから商品』『レビューから別のレビュー』といった導線を生むため、サイト内の回遊性を高めることができます。
また、ハッシュタグはUGCのカテゴリー分けを実現する側面があり、ECで扱う商品にも有効です。デフォルトで設定された商品情報に加え、自由度の高い項目を設定したい場合などに活用できます」(山崎氏)
アパレルであれば、トップスやインナーなどのジャンル、メンズ/レディース、サイズといった項目が定型のカテゴリーだろう。こうしたデフォルトの項目に加えて、たとえば「テレワーク」のような従来と異なる属性を容易に追加できる点が特徴だ。