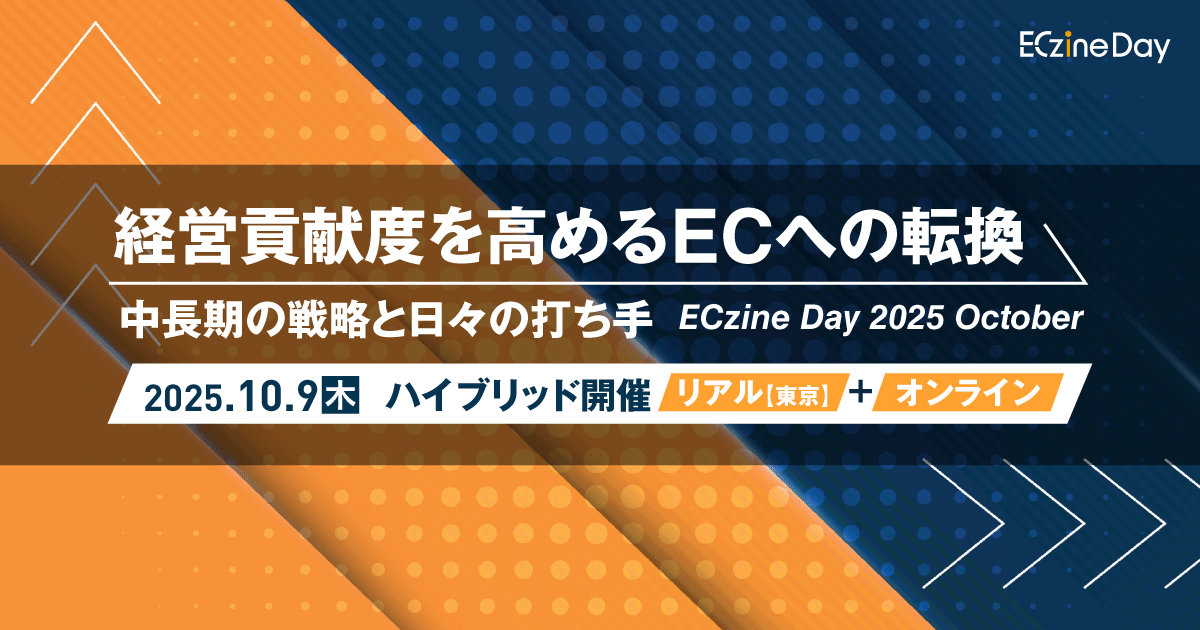SNSなしに語れない 「PAL CLOSET」急成長の背景を振り返る
──現在、50以上のブランドを運営するパルは、SNS発信を行うスタッフの多さだけでなく、それぞれが個性を生かして投稿している点が特徴的です。こうした取り組みは、いつどのようにして始まったのでしょうか。
堀田(パル) 2015年頃に、店舗で働く一部のスタッフが自発的に活用を始めたのがきっかけです。ちょうどInstagramが日本に上陸した後、市民権をもち始めたタイミングでした。彼らのフォロワー数が徐々に増えるにつれ、来店客が増え、売上に貢献している様子が見え始め、「これはチャンスだ」と思ったのです。
私自身、パルに入社する以前はファッションメディアに携わっていた経験もあり、スタイリストやバイヤーなど「個」が発信するコンテンツのほうが多くの人の目に触れやすい感覚をもっていました。時代の流れを見ても、「誰が語るか」が今後より重要になるはずだと感じていましたし、パルで働く個性豊かなスタッフが情報発信のノウハウを身につけ、全員が再現性をもって取り組めれば大きな強みになると考え、制度構築なども含めて推進し始めました。

──しかし、2015年当時のEC売上高は年間約50億円、EC化率も5%とまだ成長途上だったかと思います。店頭集客にも貢献するとはいえ、店舗で働くスタッフのリソースをオンライン上での発信へ使うことに対し、社内での反発などはなかったのでしょうか。
堀田(パル) まさに、当時のパルはまだプロモーションも売り方もオフライン主体でしたが、既に世の中のデジタルシフトは始まっていました。「このスタイルを変えていかなければ」「広告集客だけに頼らない新たな伝え方や売り方を模索しなければ」と考える一方で、世の中的にありがちといわれていた「店舗 vs EC」の構図にならないよう、双方で頑張る人がきちんと評価される仕組み作りをしなければという思いも、もちろんありました。
そこで、理解を得るために全国を回って草の根活動をしつつ、フォロワー数に応じて手当を支給するなどといった評価制度の改定や、スタッフ投稿がECサイトの流入・売上にどれだけ貢献しているかを可視化する仕組みの構築、こうした活動を表彰する場の創出や教育体制の整備などを2017年から2018年頃までに行っていきました。
奇しくもこうした体制構築をした後にコロナ禍に直面しましたが、あらかじめデータで会話ができる環境や、スタッフがオンラインでアプローチする術をもっておいたのは非常に良かったと思います。「店舗に出勤してもお客様が少ないのであれば、SNSで接客をしよう」「どんどんSNSで発信をしていこう」と呼びかけ、ECサイトに送客してもらうことで店舗で働くスタッフがEC化率向上に大きく貢献してくれました。結果、約10年でEC化率は5%から40%超に、売上も約50億円から500億円超と10倍にまで成長しています。今では、1,800人のスタッフがSNSアカウントをもち、総フォロワー数2,000万人以上の大きなコミュニティが育ちました。