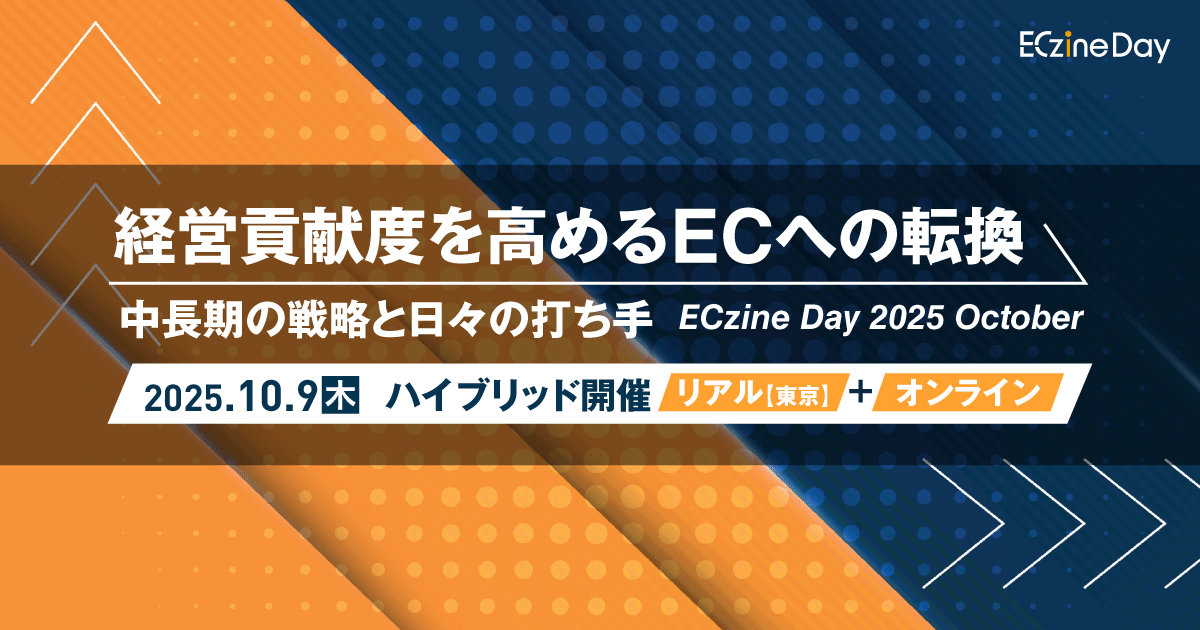ステルスマーケティング(ステマ)とは、特定の商品やサービスを消費者に宣伝と気づかれないように広告・プロモーション活動を行ったり、作為的な口コミを実施したりする行為を指す。情報発信において企業の介在があることを消費者に隠したり偽ったりした行為のすべてを指し、SNSやインターネットへの投稿など幅広い表示が該当する可能性がある。2023年(令和5年)10月1日に施行された景品表示法の改正(ステマ規制/「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準制定)にともない、新たに不当表示に指定された。
悪質とされるステルスマーケティング(ステマ)の手法は、大きく二つある。一つは関係のない第三者を装い自社の製品を宣伝する「なりすまし型」で、口コミサイトに正体を偽って情報を投稿する場合などが該当する。もう二つ目は「利益提供型」で、芸能人やインフルエンサーに報酬を支払い、好意的な情報を投稿させる場合が当てはまる。
ステマ問題が提起された背景には、昨今のブログやSNSの普及による消費者への口コミの影響力の大きさがある。ステルスマーケティング(ステマ)を実施する企業・ブランドが出現することで、消費者は適切な情報収集や正しい購入判断が困難になる可能性が高いことから、市場への悪影響が懸念されている。
ステマ規制施行後は、悪意なくステルスマーケティング(ステマ)に該当するマーケティング・PR施策を実施してしまった場合も罰則が課せられる恐れがあるため、注意が必要だ。消費者庁はウェブサイトにて景品表示法に基づく措置命令を下した企業の実名や、ステマ規制に該当した行為の詳細を「お知らせ」内の「報道資料」ページにて公開しているため、たとえ故意でない場合でも事態の発覚により企業・ブランドにネガティブなイメージがつくなど悪影響を及ぼす可能性がある。
なお、ステマ規制に該当(違反)すると判断された場合は、当該行為の差し止めや再発防止措置の明示をしなければならず、措置命令に従わない場合は2年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられる可能性がある。また、ステマ規制に該当する表示内容にさらに「優良誤認」「有利誤認」といった不当行為が含まれる場合は、さらに100万円以下の罰金が科せられることもある。
同じカテゴリの他の用語
ステルスマーケティング(ステマ)に関連するおすすめ記事
Special Contents
AD