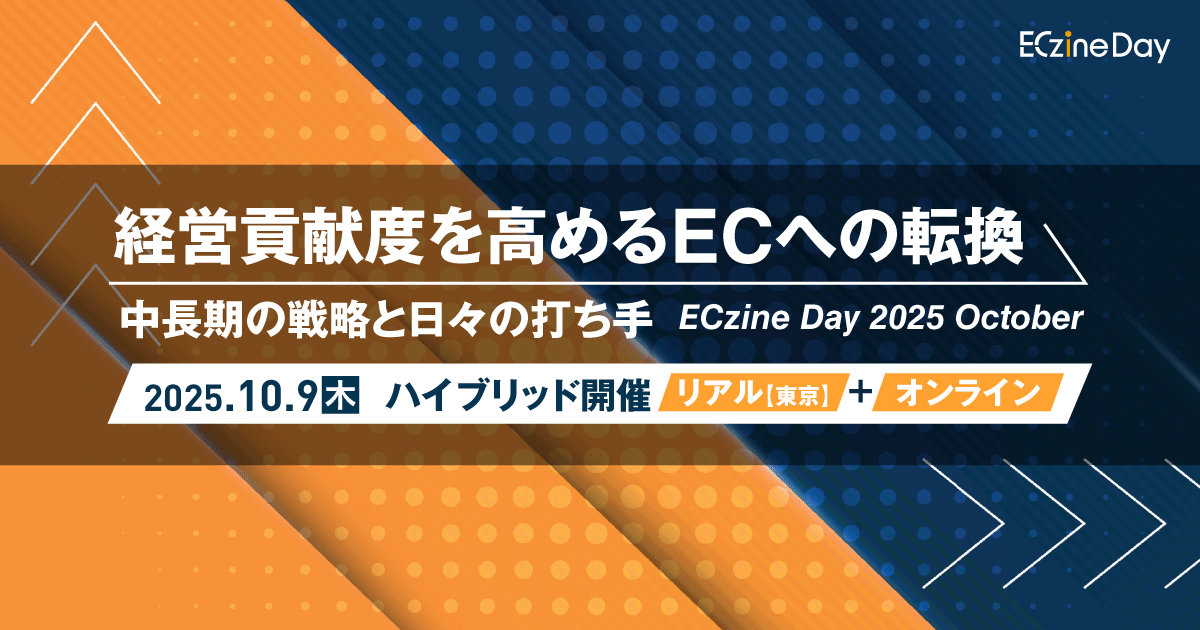特定商取引法は「特定商取引に関する法律」の略称で、1976年に消費者の利益を守るために施行された法律である。事業者による違法性の高い取引や悪質な取引を取り締まることに焦点を置いており、時代に合わせた改正を重ね、直近では2021年(令和3年)に改正する法律が成立。多くの項目は2022年(令和4年)6月1日に施行され、事業者が交付すべき書面の電子化対応のみ、後を追う形で2023年(令和5年)6月1日に施行されている。
特定商取引法では、訪問や電話での販売や通信販売など、7種の取引分類が定義されており、事業者が知っておくべき禁止事項やクーリングオフ制度など消費者を守るルールが定められている。
たとえば「氏名等の明示の義務付け」というルールがあるが、法令を遵守しているECサイトではこのルールに基づき、サイト内に「特定商取引法に基づく表示」のページが作られている。
また、広告表示に関するルールの策定や誇大広告の取り締まりも、日本では特定商取引法に基づいて行われている。特定商取引法に違反した場合、業務停止命令や業務禁止命令が執行される可能性もあるため、注意が必要となっている。近年はEC取引が急激に増加したことでトラブルも増えており、これを踏まえてeコマース(EC)に関するルールの見直しも進められている。
なお、サブスクリプションビジネスの普及に際し、無料契約から有料契約への自動移行に関する手続きも規制対象となっていることから、EC事業者は目を通しておくべき法律といえる。
2021年(令和3年)以降の主要改正項目と概要まとめ
- 送りつけ商法への対策(令和3年7月6日施行):注文や契約をしていないにも関わらず、販売事業者から一方的に送られてきた商品について、消費者に金銭支払義務が生じない旨を明文化。さらに、商品の開封や処分をした場合も、販売業者の返還請求権を否定できる旨が記されている。
- 通信販売における詐欺的商法への対策(令和4年6月1日施行):「定期購入でないと誤認させる表示(定期性誤認表示)等に対する直罰化」「定期性誤認表示によって申込をした場合に申込の取り消しを認める制度の創設」「通信販売の契約解除の妨害に当たる行為の禁止」に該当する表示や解除の妨害行為を適格消費者団体の差止請求対象に追加。
- クーリング・オフ通知の電子化(令和4年6月1日施行):消費者からのクーリングオフ通知について、電子メールやアプリのメッセージ機能、ウェブサイトによるフォームを用いた通知など、電磁的方法で行われた際にもその通知が有効となる旨を追加。旧特商法では、書面による通知のみを有効としていたが、「書面又は電磁的記録」となった点が改正の大きなポイントとなっている。
- 外国執行当局の情報提供制度等(令和4年6月1日施行):越境ECなど、国際的な電子商取引の規模・機会が拡大したことを踏まえ、外国執行当局との情報交換・提供による実行的な法執行を実現するため改正。一定の要件を充足した場合に、日本の行政当局からも外国執行当局に対する情報提供を行うように内容が変更されている。
- 事業者が交付すべき書面の電子化(令和5年6月1日施行):事業者が交付しなければならない契約書面などについて、消費者の事前承諾を得た上で電子メールやアプリのメッセージ機能、ウェブサイトによるフォームを用いた通知など、電磁的方法での実施が可能に。旧特商法では書面による交付が求められていたが、選択肢が増えた点が変更点となっている。
同じカテゴリの他の用語
特定商取引法(特商法)に関連するおすすめ記事
Special Contents
AD