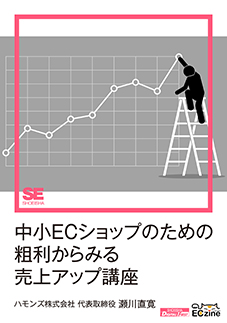「意味に出合い、意志を買う」。このような言葉を提唱し、次世代の店舗のありかたを提案するメディア型OMOストア「CHOOSEBASE SHIBUYA」が2021年9月、渋谷にオープンした。「新しい出会いと学びのあるストア体験の提供」をコンセプトにした同ストアを運営するのは、株式会社そごう・西武だ。同社初のRaaS業態を採用するのみならず、実店舗とECの完全在庫連携を実現するなど、同ストアは従来の百貨店のイメージから大幅なアップデートを果たしている。なぜ今、このようなストアを渋谷という街にオープンしたのか、取り組みによって目指す先などを、CHOOSEBASE SHIBUYA ディレクターを務める伊藤謙太郎さんに聞いた。

「もったいない」を変え 百貨店の課題解決へ
高度経済成長期の頃から築き上げられた、百貨店のイメージ。広いフロアに多種多様なブランドが入店し、来店した顧客に対して接客をする。店舗に多く顧客が訪れる時代には、こうした接客・販売手法が主流かつ有効であったが、ECが普及し、顧客に選択肢が与えられた現代においてこうした「待ちの姿勢」で売上を作ることは難しい。伊藤さんは「長い年月をかけて築き上げ、守ってきた従来の百貨店のビジネスモデルが、現代にフィットしていないと外にいた頃から感じていました」と語る。
広告代理店、SIerを経て、2018年にそごう・西武に入社した伊藤さん。百貨店をシステム面から支援する立場で仕事をする中で、向き合うべき課題や解決策を思い浮かべながらも、自身の立場では実行につなげることが難しく、「事業会社の中に入り、自分がビジネスをより良くする立場に回りたい」と考えたと言う。とくにビジネス規模が大きい事業会社の場合は、意思決定をするにあたってもさまざまな制約が存在する。こうした事情を理解しながらも、「消費者視点でもったいないと感じることは変えていきたい」と思い、選んだのがそごう・西武であった。
伊藤さんは、「さまざまな課題の中でも、オンラインとオフラインの分断をなくすことに目を向けていた」と語る。そごう・西武では、伊藤さんの入社当時からすでにECが販路として存在していたものの店舗との 在庫連携ができておらず、取扱商品も運用も、店舗とECが分断した状態となっていた。
「店舗で展開されている編集力がEC上では発揮されず、ただ商品を置いているだけの売場になってしまっている。これは非常にもったいないと感じました。ブランドと顧客をマッチングさせる売場演出をオンラインにも還元しなければ、機会損失となってしまいます。
とは言え、基幹システムをはじめ既存の百貨店のオペレーションは長い歴史をかけて最適化されたものとなっており、すぐに改善することは事業規模の大きさからも難しいのが現実です。『百貨店のデジタル化』を自身のミッションとして掲げながらも、まずはできるところからと考え、店舗とECを統一した売場を作りたいと考えました。経営陣にも『今後のために新たなチャレンジをしたい』と伝えて新規事業の立ち上げを提案し、それがCHOOSEBASE SHIBUYAにつながったというわけです」
同ストアの構想を練るにあたり、伊藤さんは百貨店がこれまで十分に接点を創出できていなかったデジタルネイティブ世代へのアプローチも模索した。20代の若手社員をプロジェクトメンバーに加え、意見交換をする中で伊藤さんにも気づきがあったそうだ。
「僕が想像する以上に、若い世代には『SDGs』や『サステナブル』という言葉が浸透していることが判明しました。彼らの行動を観察すると、レジ袋有料化以前から買い物時にショッパーをもらわずにエコバッグを使う人もいれば、問題意識を持ちながらも具体的に何をしたら良いのかわからないという人もいて、意識と行動の間に差があることも見えてきたのです。また、商品についても『便利』『安い』といった軸から選ぶのではなく、『自分に合ったもの』を選びたいと考える人が多いことがわかりました」
このように既存の課題と新たにアプローチしたいターゲットが持つ潜在的な意識、そしてそごう・西武が持つ売場の編集力がかけ合わさった結果行き着いたのが、オンラインとオフラインが融合したメディア型OMOストアという形態である。時流を鑑みて都度新たな商品との出会いを生むべく、半年ごとに打ち出すテーマを変える方式での運営とし、「出店ブランドや取扱商品もテーマに合ったものを揃えるようにしていく」と伊藤さんは説明する。
「第1弾のテーマは、『TIMELIMIT』としています。前出したSDGsやサステナブルというキーワードをどうしたら具体的な行動に落とし込めるか考えた際、若い世代を中心に支持が広がりつつあるD2Cブランドの存在が目に入りました。作り手の想いが込められたD2Cブランドには、製造の裏側が自然環境に配慮されたものであったり、さりげなくサステナブルな仕組みが取り入れられていたりと、地球の未来を考えながら運営されているものが多数存在します。こうしたブランドと触れる場を作り、より自分ごと化してもらうために、『地球環境は待ってくれない』というメッセージを端的にテーマやビジュアルに落とし込みました」