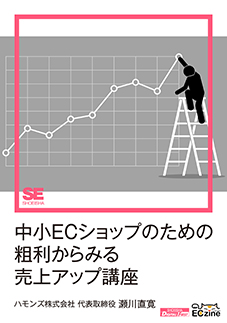フラクタは、ECを軸としてD2Cブランドの立ち上げや成長を支援している。戦略策定からマーケティングコミュニケーション設計、ECサイト制作までを一貫して手がけており、「日本のブランド価値の総量を増やす」をミッションに掲げるブランディングエージェンシーだ。
河野氏はフラクタについて「一般的にブランディングというと、クリエイティブを設計する、世界観を醸成するという側面が大きいように感じるかと思いますが、フラクタではその企業自身が成長し続けられることを目標に、ブランドビジネスそのものを、ともに創っていく姿勢で活動をしています」と話す。
なお、河野氏は土屋鞄製造所のデジタル戦略担当の取締役も兼任しており、ECプラットフォーム「Shopify」のエバンジェリストも務めている。
ECにネガティブなイメージがある5つの理由
河野氏はまず、「ECにネガティブなイメージを抱く方も多いのではないでしょうか?」と参加者に尋ねた。これには主に5つの原因があるという。
ひとつは、自由度の低さだ。
「ECカートシステムやASPの自由度が低かったり、開発会社やパッケージに依存せざるを得ないことで、デザインに介入できるシーンが少なくなり、ECサイト自体の自由度が低く認識されているように思います」
ふたつめは、管理の煩雑さ。ECサイトは一般的にページ数が膨大になることもあり、開発会社やデザイン会社、プロジェクトマネージャーなど、多くのメンバーがチームに関わることになる。こうした事情によりECサイト全体を管理するのは手間がかかる、というイメージが生まれると河野氏は指摘した。

3つめは、個人情報をはじめ、ECで取り扱う情報にはセンシティブなものが多いため、情報の取り扱いに慎重にならなくてはいけないこと。4つめに挙げたのは、努力が評価されづらい点だ。ECに関わる事業が順調に進んでいるときは問題ないが、なかなか頑張りが評価されなかったり、何度作り直しても喜んでもらいにくいといった背景があるようだ。
そして5つめは、作り手から見て「ECが単純につまらなそう」というイメージがあること。河野氏もたびたびこの手の質問を受けるという。
これらを踏まえたうえで、「これまでのECは、確かにこうした側面を持っていました」と河野氏。だがそのあとに「これからは違う」と強調した。
これからのECは自由度が高くなる
では、今後はどうなるのか。河野氏は新しいECのありかたについて、オーストラリア発祥のブランド「コアラマットレス」を例に挙げて説明した。コアラマットレスのECサイトは、ECプラットフォーム「Shopify」を活用している。
そもそも一般的なECサイトは、カートシステムを使って構築されており、それをカスタマイズしたり、デザインのみを変えて運用することも多いという。ただしいままでは、ECシステムのベンダーにカスタマイズを依頼すればコストが上がる、デザインの自由度が低くなるなどの制約が存在した。
一方、Shopifyの仕組みは、河野氏いわく「表側と裏側がAPIで分離できる点が異なる」とのこと。具体的には「たとえば『カートに入れて決済する』という部分の機能だけを利用し、残りのフロント側やそのほかのシステムとのつなぎこみも、APIを利用して行うことができる」のだ。こうした仕組みは「ヘッドレス・コマース」と呼ばれ、デザインや開発側の制限を最小限に販売を行うことができるため、トレンドとしても注目されている。
「いままでは、カートシステムのデベロッパーやベンダーが、その部分に責任をもっていたので、デザイン側が出してきた要項のうちリスクがあるものは受けられなかった。ですがShopifyのような仕組みでは、フロントエンドとバックエンドが分離されていることで、デザインサイド、開発側双方の要望に応えることができる、という点が大きな違いです」

では、コアラマットレスのECサイトにはどんな特徴があるのだろう。
「コアラマットレスでは、顧客向けのウェブサイトのフロントエンドと、顧客向けのコンテンツマネジメント、すなわち割引などを提供する仕組みや決済、在庫、ロジスティックス、分析レポートなどで別々の外部サービスを利用しています。そのため特定のサービスに依存することなく、新しいサービスに一部分だけを乗り換える、といったこともできるのです」
“E”Cだけではダメな時代へ
ECの自由度が増すことで、デザイナーやエンジニアがより挑戦できるような環境が整ってきている点も重要だと河野氏は指摘。アメリカを中心に急成長している「D2C(Direct-to-Consumer)」なるビジネスモデルを支えたのはテクノロジーとクリエイティブであるとし、「これからはECを作ること自体ではなく、EC上でどうコミュニケーションを図るのかが重要になる」と語った。
「アメリカでD2Cに取り組む企業は、EC自体にお金をかけるのではなくて、ECでどういうコミュニケーションをするか――たとえば、クリエイティブディレクションやライティング、3D、動画などに注力しています。要するに今までお金をかけることが難しかったクリエイティブの部分に予算を割いているのです」
また、テクノロジーを活用したこうした変化によって、オフラインに対してのコミュニケーションも変わってきたという。スニーカーのデザインをカスタマイズできるツールが、バックエンドのデータと連携する。EC上でもっとも視聴されている動画やルックブックなどを店頭のディスプレイで表示する……。そういったことが実際にアメリカで行われていると河野氏は紹介した。
「ECでは、実際のお店や販促物など、リアルも含めたすべてのクリエイティブを製作することが求められています。4~5年くらい前まではデジタルの比重が高く、『ECを作れば売れるだろう』と言われていた時代もありました。しかし、いま売上をあげるためには、OMOという言葉で語られるように、リアルなコミュニケーションを含めてどう設計するのか、を考え実行することが求められています」

たとえば、河野氏が取締役を務める土屋鞄製造所では、商品が実際にどのように使われるかを動画で紹介している。こういった動画は同社内のスタッフが撮影している。
「こうした取り組みを行うには、動画を撮影するスキルが必要になるし、クリエイティブを自社で作成するスキルも必要になってきます。また、ブランド自身が体験イベントを実施することも、ユーザーに世界観を体験してもらううえで重要です。このような取り組みを、いかにコンパクトに低コストに行えるかも大切になってくるでしょう」
これからのECでカギを握るのはデザイナーやエンジニア
河野氏は、上述したような取り組みを実現していくためには、テクノロジーとクリエイティブのリソースがまだまだまったく足りていないと指摘。
「いままでは自由度があまりないように見えてしまっていたECの世界で大きな成功をもたらすためのキーパーソンは、デザイナーやエンジニアだと僕は思っています」
また、ECでモノを買うということが当たり前になったいまだからこそ、よりリアルの場で「体験」することが重要になってきていると河野氏は語る。一般的なECシステムを活用し、「自動販売機のようにただ商品を売るのはもはや時代遅れになりつつある」なかでポイントとなるのが「シンボリック・エクスペリンス(以下、SX)」ではないかと河野氏は考えを明かした。
フラクタではSXを「ブランドならではの象徴的な体験」と定義しており、デザインといった視覚だけではなく、味や香り、音、手触りまでを含めた体験のことを指している。UIよりは広く、ブランド体験よりは少し狭い範囲のイメージだという。

そういった体験を生むために必要なのは、「体験の連続性をつくるアイディア」だという河野氏は、例として「ぬま田海苔」をあげた。店頭で海苔を焼き、その香りをかぐ、という体験をとおして、香りを記憶に留めてもらえるよう心がけているそうだ。
「こうしたリアルな体験を、ARやVRといったテクノロジーを活用して設計していくことが今後は必要になっていくでしょう」
クリエイターがECに携わるメリットとは
河野氏はデザイナーやエンジニアがECに携わるメリットとして、以下の3つの内容をあげた。
ひとつめは、実際にモノを売り、広告費がいくらで、あるひとつの機能がどれほどユーザーに利用してもらえるか、などを体感することで、ビジネスの全体像をインスタントに体験できること。
ふたつめは、世界に対して商売ができること。日本国内の需要が下降気味であるため、日本のモノを販売する市場を、世界へと広げていく必要がある。今後はますます、越境ECの仕組みが必要になるだろうと、河野氏は語る。
3つめは、成果物を世界に体験してもらえること。世界に向けてモノを販売していくことが当たり前になっていけば、当然のことながら、自身が作ったサイトのデザインや開発した機能が世界中のユーザーの目に触れたり、評価されるという体験をすることもできるはずだ。

これらをふまえ、河野氏は下記のようなメッセージとともに講演を締めくくった。
「いま、ECにはプレイヤーがたくさんいますが、みんなひとつの壁にぶち当たっているように思います。クリエイティブやテクノロジーの枠組みを超え切れていないんですよね。だからこそ、コマースの世界で皆さんの力をもっと借りたい。そう僕は思っています」