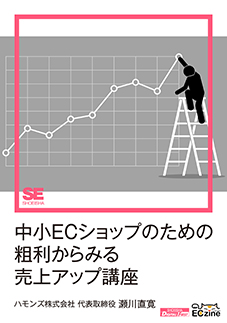リアル店舗でのチェックインが顧客の能動的なアクションを引き出す
パーソナライズされた情報提供システムの意図として、中野氏は「顧客に能動的なアクションを取ってもらうことが鍵になると考えた」と語る。
従来型の店舗では、店舗スタッフが来店客に声掛けをするシチュエーションが多く、どうしても受動的になってしまっていた。しかし、自分が買い物をする際には、その時の気持ちや関心事などに基づいてコミュニケーションをすることで、良い買い物をしたいと考えるものだ。それを実現するために、店頭にチェックイン筐体をおいて、それにスマホアプリをかざすという能動的なアクションを取る形にしたわけだ。
「パーソナライズされた情報が掲載された店舗専用画面で、自分の気持ちを再認識し、例えば店舗スタッフに伝えやすくなるなど、体験のきっかけを作ることができるのではないかと考えた。これによって、体験だけではなく顧客の心境にも変化が生じるのではないかと期待している」と中野氏は語り、それを受けて岸氏も「服を買いに店に入るのは、どこかアウェー感があるもの。服を触ると声掛けされて、それが苦手という顧客も多い。また、店舗スタッフも顧客が何を望んでいるのかわからないうちに売るために声をかけなくてはならない。その関係性がとても不幸だと感じ、それを解消したいという思いがアプリにつながった」と思いを語った。

そして、岸氏は「『店頭という場の主導権を顧客に渡す』ために、チェックインから始まる形式になっているものの、スタッフ側も、顧客に合わせて顧客の体験をサポートする側にまわるという、気持ちと行動変容が生まれることを期待している」と続け、「今後もそうしたコミュニケーションのきっかけになるような施策を厚めに行っていきたい」と語った。
そして能動的になることで、顧客側の意識の変化も期待される。たとえば、データをナノ・ユニバースに預けているという感覚、そしてそれを更新していく感覚だ。もちろん、サービスを受けたい人はデータを預け、必要ない場合は預けない選択肢を用意し、利用者がそれを選べるようになることが大前提ではあるが。
中野氏は「一般の生活者がその感覚を持つのはまだ先かと思う」と前置きしつつも、「データを預けることで自分にメリットが還ってくる関係性が明確になれば、顧客データの取扱いについて新しい観点や関係性が切り拓かれるのではないか」と期待を寄せた。