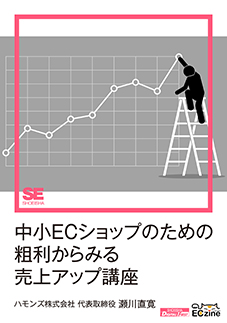顧客とともに進化してきたナノ・ユニバースのDXの歴史
「自分たちの商品やサービスの感情的な価値を伝える、そのために顧客をよく『知る』ことから始める」。それが本施策を通じて最も重要だった――。そんな言葉から本セッションはスタートした。
TSIホールディングスは、売上1,341億円のうちECの売上が406億円を占め、924店舗を擁する一大アパレルグループだ。レディス、メンズ、ゴルフ、ストリート、コスメ、飲食まで、ブランドのポートフォリオの幅広さと、マスからコアまで豊富なアセットを強みとしている。その中で「ナノ・ユニバース」は売上104億円、EC化率が52.5%、自社EC売上のうちアプリ経由での売上が45%を占め、アプリダウンロード数は約84万にも上る。TSIの岸氏は「この規模の事業としてはEC化率が高く、アプリが根付いており、グループ内のDX施策を牽引するブランドといえる」と評する。


こうしたDX化の背景には、欲求の変化、生活者のパラダイムシフトなどとも表現される、「消費行動の変化」がある。モノが不足していた時代ではモノへの欲求が高く、物質的充足が買い物の目的だった。それがモノや情報があふれる時代になり、利便性への欲求が高まり、機能的充足が求められるようになり、さらに同質化が進み、デジタルでの購買体験は非常に面白みがなくなっているといわれる。
岸氏は「今後、未来においては個人的価値の欲求が高まり、情緒的な価値などに意味を見出すようになるのではないか。その際に、個人的価値は人によってまったく異なり、多様化が進むことは間違いない。それに対し、適切な施策を当てていく必要がある。そのためにはやはり顧客理解が必要だと考えている」と語る。
そうした考えかたのもと、ナノ・ユニバースでは顧客ニーズに合わせて、2015年頃からOMOやオムニチャネルを前提に、施策を拡大してきた。たとえば、リアル店舗への来店数が減ってきたことを受けて、来店ポイントを開始して来店を促したこともそのひとつだ。また、ECの利用が進む中で、店頭で顧客がスマホの画面を見せながら商品について尋ねるケースが増えたことを受け、アプリでスクリーンショットを撮ると品番と品名が自動的にテキスト表示される機能が設けられた。

岸氏は「コロナ禍では店の混雑情報をアプリでお知らせしたり、OMOでスタッフ基軸の販売強化施策として来店予約などもできるようになった。そして昨今は、リアルにチェックインすることで、店舗体験を楽しんでもらう施策に取り組んでいる」と語り、「顧客ニーズに合わせその都度対応することが、これまでのナノ・ユニバースのDXの歴史だった」と振り返った。
オン・オフの行動データを「KARTE」でワンストップ連携
ナノ・ユニバースのDX施策について、2015年から参画しているのがプレイドだ。2011に創業し、2015年に顧客体験プラットフォーム「KARTE(カルテ)」の提供を開始しており、TSIはローンチ直後から導入しているという。KARTEは、リアル店舗で普通に行われているような人対人のコミュニケーションや接客をオンラインでも実現することを志向している。
顧客のリアルタイムな行動や感情を解析し、それに合わせた施策を配信するという考えかたに基づいている。ECサイトやアプリなどのオンライン上でKARTEが解析可能な情報(例:顧客がその瞬間に滞在しているページや流入経路など)とKARTEの外部で保持している情報(例:POSで保持している購買データなど)をKARTEで突き合わせすることで、顧客をセグメント分けし、現在ではオン・オフ問わずその顧客に合った施策を配信できるようになっている。

当初KARTEのセールスとしてTSIの施策に参画し、現在実装中のリアル店舗へのチェックイン体験施策においてプロダクトマネジャーを務める中野氏は、「KARTEでは、リアルタイムに顧客1人ひとりのデータを解析し、それを分析して人として可視化、実際のアクションまでワンストップでつなげていける。今回はさらにOMO的な文脈で、実店舗で顧客が体験する施策に還元するところまで進めている」と語り、「以前からナノ・ユニバース様にはKARTEを活用いただき顧客行動データを解析・蓄積していたが、2021年11月末のチェックインや店舗専用画面のリリースで、より顧客の体験を点から線として、パーソナライズされた価値を提供できるようになった」と述べた。

店舗専用のアプリ画面には、既存のチェックイン“来店スタンプ”機能が表示され、そこにスタンプを押して“チェックイン”することで、新たにさまざまな店舗専用ページが利用できるようになった。店舗専用ページには、店舗の情報と顧客の行動情報が紐づけられており、パーソナライズされた内容になっている。参照データとしては、ナノ・ユニバースが持つ「POSデータ」、KARTEで分析された「Web閲覧履歴」、商品マスター情報による「入荷日」、顧客自身が登録している「お気入り欄」などがあり、それらを掛け合わせていくことで、「店内のベストセラー」や「おすすめのコーディネート/アイテム」、「店内の新着商品」、「お気に入りの商品」などが表示されるようになっている。

中野氏は「これまでの店舗体験では、たとえばWebサイトでは当然表示されている『ベストセラー』も閲覧が難しかった。そうした情報の非対称性のようなところをうまく解消していくことも、この施策の狙いのひとつ」と語った。

リアル店舗でのチェックインが顧客の能動的なアクションを引き出す
パーソナライズされた情報提供システムの意図として、中野氏は「顧客に能動的なアクションを取ってもらうことが鍵になると考えた」と語る。
従来型の店舗では、店舗スタッフが来店客に声掛けをするシチュエーションが多く、どうしても受動的になってしまっていた。しかし、自分が買い物をする際には、その時の気持ちや関心事などに基づいてコミュニケーションをすることで、良い買い物をしたいと考えるものだ。それを実現するために、店頭にチェックイン筐体をおいて、それにスマホアプリをかざすという能動的なアクションを取る形にしたわけだ。
「パーソナライズされた情報が掲載された店舗専用画面で、自分の気持ちを再認識し、例えば店舗スタッフに伝えやすくなるなど、体験のきっかけを作ることができるのではないかと考えた。これによって、体験だけではなく顧客の心境にも変化が生じるのではないかと期待している」と中野氏は語り、それを受けて岸氏も「服を買いに店に入るのは、どこかアウェー感があるもの。服を触ると声掛けされて、それが苦手という顧客も多い。また、店舗スタッフも顧客が何を望んでいるのかわからないうちに売るために声をかけなくてはならない。その関係性がとても不幸だと感じ、それを解消したいという思いがアプリにつながった」と思いを語った。

そして、岸氏は「『店頭という場の主導権を顧客に渡す』ために、チェックインから始まる形式になっているものの、スタッフ側も、顧客に合わせて顧客の体験をサポートする側にまわるという、気持ちと行動変容が生まれることを期待している」と続け、「今後もそうしたコミュニケーションのきっかけになるような施策を厚めに行っていきたい」と語った。
そして能動的になることで、顧客側の意識の変化も期待される。たとえば、データをナノ・ユニバースに預けているという感覚、そしてそれを更新していく感覚だ。もちろん、サービスを受けたい人はデータを預け、必要ない場合は預けない選択肢を用意し、利用者がそれを選べるようになることが大前提ではあるが。
中野氏は「一般の生活者がその感覚を持つのはまだ先かと思う」と前置きしつつも、「データを預けることで自分にメリットが還ってくる関係性が明確になれば、顧客データの取扱いについて新しい観点や関係性が切り拓かれるのではないか」と期待を寄せた。
店舗は『顧客と一体化する場』へ 全チャネルでシームレスな「快適な購買体験」提供へ
ここまで紹介してきたような施策によって、TSIが目指しているのは「顧客の『個』に寄り添うOMO」であり、その実現には「顧客体験の連続性」が不可欠となる。つまりは、顧客を理解して、デジタルと店舗、モバイルとPCといったチャネルをシームレスな体験としてつないでいくことが重要なのだ。

基本的には、来店予約し、来店し、店内でさまざまなアクションをとり、退店後にフォローアップ……という流れは、一般的なアパレルの購買行動としてどのような企業でも共通している。だからこそ、何かを強いることなく、「いつもの通りの買い物」でさまざまなサポートを実施できるようにすることが必要になるだろう。そして、そのためにはデータが必要であり、あらゆるタッチポイントのデータを取得・収集し、統合するKARTEが重要な役割を果たすことは間違いない。
たとえば、Webの行動データを取得しても、Webブラウザを閉じれば“Webからの離脱”になり、店舗に来ても購入せずに出てしまえば“店舗からの離脱”になる。しかし、それらのチャネルでの行動がデータでつながれていれば、顧客の行動やインサイトを理解し、より的確なサポートが可能になるだろう。そのためには、これまでアナログだったオフライン側での行動をどれだけデータ化できるかがポイントであり、さらにはKARTEのような施策実行基盤でオン・オフラインを連携させることが重要となる。

岸氏はあらためて、「自分たちの商品、サービスの感情的な価値を伝える。そのために顧客をよく『知る』ことから始める」と繰り返し、「顧客1人ひとりの行動から趣味趣向をしっかりと把握し、その次のサービスに活かしていく。そのためにはデータを突き合わせる『KARTE』のようなプラットフォームが重要であり、これからのOMOの骨子になることは間違いない」と強調した。
中野氏も、「オン・オフラインの接点をどう立体的に配置するか。店舗スタッフやデジタルマーケティングの担当者含め、それぞれのタッチポイントで知り得る情報を横断的につなぎ、どのタッチポイントでも情報が共有され、それを元にした接客が受けられるようにすることが非常に大きなポイントになる」と語る。岸氏はそれを受けて、「スタッフ側にも共有するための画面などを準備する必要がある。それにより、スタッフの接客も大きく変化する。売るための接客から、商品のストーリーやスタッフ自身の情熱を熱く語ったり、的確なサポートを行う接客に変わるだろう。それがかなえば、店舗は『顧客と一体化する場』になっていく」と語った。
店舗の価値も「レジをどれくらい商品が通過したか」という見方から、「最終的に売上にどのくらいつながったか」という評価に変わる可能性もある。いわばメディアとしての役割や価値が増大するわけだ。 最後にセッションを振り返り、岸氏は「OMOを考えると、顧客の“個”とスタッフの“個”というふたつの“個”が出会い、つながり、体験という価値を提供することができればと考えている。たとえば、美容師のようにずっとその顧客に寄り添い、顧客もその人に会いに来るというお店をつくることができたら」と今後の展望を語った。
そして、中野氏も「そのためには、各ブランドや各サービスに対する顧客の期待値を的確に捉えることが大切になる」と改めて強調し、セッションを終えた。