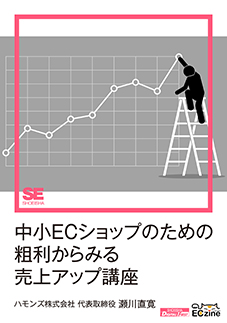CXの質の向上に欠かせない“透明性”の観点

“オムニチャネル”という言葉が登場して久しい。しかし、定義があいまいで定着しきらないまま、O2O(Online to Offline)やOMO(Online Merges with Offline)、さらにはオムニチャネル2.0という言葉も現れ始め、本来期待されていた価値が現実になっていなかった。
「言葉自体が先走ってしまったと思います。その点は失敗だったかもしれませんが、今まさに概念として定着するタイミングだとみています」と、ZETAの山崎さんは解説する。
オムニチャネルと言われ始めた当初は、あたかもオンラインとオフラインをつなぐ画期的な方法のように受け入れられていたが、実際にできることはECで決済した商品をコンビニで受け取る程度で、在庫管理や配送など限られた領域でしか機能していなかった。「本当は、さまざまなチャネルでのユーザー接触をシームレスに行えるという意味なので、以前の状態では“オムニチャネル”と言うには大げさだったのでは」というのが山崎さんの見解だ。
「だから今になって聞くと、古くさく感じてしまうところはあります。ECzine読者ならなおさらでしょう。ただ、概念としては間違いなく重要です。ECがますます拡大する中、『オンラインかオフラインか』あるいは『ECか店舗か』と対抗する姿勢になってしまい、売上を取り合うような状況は顧客視点ではありません。コマースという大きな傘の下にオンもオフもあると捉えて、ユーザーが納得いく買い物をできるように支援する必要があると思います」
ブランド側であってもリテール側であっても、ユーザーの納得いく買い物を手助けすれば、それはすなわち顧客体験の質の向上につながる。ZETAではかねてから顧客体験、すなわちカスタマーエクスペリエンス(CX)の重要性に注目し、ソリューション群の名称にも冠してきた。サイト内検索エンジンの「ZETA SEARCH」をはじめ、レビューエンジン「ZETA VOICE」など5つのソリューションを「ZETA CXシリーズ」として展開している。イトーヨーカ堂やヤマダ電機といった、相当数の商品点数を扱う大手企業のECサイトを支援し続け、今年1月には同シリーズを導入したクライアント企業のサイトの年間流通総額が1兆円を突破したところだ。機能だけでなく、処理能力の高さと速さも厚く支持されている一因となっている。

「CXは、UXやカスタマージャーニーといった概念も包括しています。マーケティングの本質は顧客満足の向上だという点からも、数々のバズワードのように部分的に領域を切り取って廃れていく懸念がありません」と、CXを自社事業の根幹に据えた理由を話す山崎さん。加えてもうひとつ、CXを重視した理由がある。それは、“透明性”というキーワードと深く結びついていることだ。
ごく一般のユーザーが、スマホやSNSを介してまるで息をするように情報の受発信を行えるようになった時代。一方的で企業の視点に偏った情報提供は受け入れられなくなりつつあり、このままでは聞く耳も持たれなくなるのは予想に難くない。商品の認知形成や興味を持つきっかけは、企業発信ではなく第三者発信にシフトし、公平な情報源として皆がレビューを参考にするようにもなった。
そうなると、もはや企業はユーザーに対して取り繕うことができない。
「一瞬の演出で錯覚させて買わせるようなことはもう通用しませんし、後々企業の評判を落とすだけです。語弊があるかもしれませんが、私自身、そのようなマーケティングは嫌いです。マーケティングテクノロジーがいくら進化しても、顧客の可処分所得が2倍になるわけではないので、どれだけ推しても売上が倍々に伸びるわけじゃない。それなら、透明性の高い情報をいつでも得られるように整え、決定を煽ることなくユーザーに委ねて、その上で購買後も『いい買い物をしたな』と思ってもらえるように努力することが、中長期的なファンの獲得と事業成長につながるはずです」