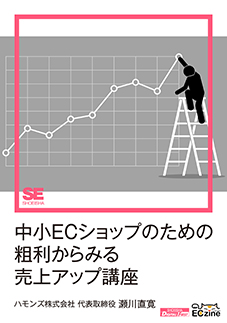顧客に「好かれ」「最初に思い出してもらう」ための体験
オムニチャネルへの取り組みとして、「店舗とECのデータ統合」「店舗のスタッフが顧客のデータを見ることができるようにする」といった施策が知られています。もちろん、顧客に良い体験をオムニチャネルで提供するためには、こうしたハード面の整備は必須になってはきます。
しかしより大切なのは、そのチャネル間で顧客が感じる良い体験を同じものにしてゆくことです。
先に、オムニチャネル化は事業をより大きくするための手段だと述べました。事業をより大きくするためには、自社の商品を何度も買ってもらい、LTV(ライフ・タイム・バリュー)を上げていくことが必要です。そしてそれは、チャネルごと(店舗ごと)の売上ではなく、その企業において顧客1人あたりの売上の合計額をいかにして上げていくかという視点で考えます。
それを実現するためには、顧客に自社を好きになってもらわなくてはなりません。そうでなければ、余程のことがない限り、利用し続けてもらうことは難しくなるでしょう。
だからこそ、企業は顧客と良い関係を築いていく必要があり、「良い体験」を顧客に対して提供し続け、満足度を上げ続ける必要があるのです。世のビジネスの先輩たちは「売上は後からついてくる」とよく言ったものですが、まさにそのことです。LTVや顧客体験に関連して、「エンゲージメント」というキーワードも出てきていますが、もともと商売の世界で当たり前に言われていたことが、横文字に置き換わっているだけです。

前回の記事で、インターネットとスマートフォンの登場によって情報が溢れ、選択の幅が広くなりすぎてしまったため、顧客がストレスを感じていると述べました。場合によっては、何かを買おうと思ったにもかかわらず、購入自体をやめてしまう可能性もあります。したがって、顧客が迷いというストレスを感じる購入の前段階で自社を思い出してもらう必要もあるのです。
脳科学よると、人間の脳は感情的に強い経験がともなった時に記憶に残るメカニズムになっています。例えば、子どもの頃にとてもうれしかったこと、悲しかったことを思い出してくださいと言われたら、ひとつやふたつは思い出せるのではないでしょうか。自社の存在も、なにか特別な体験が伴うと記憶に残ると考えられます。
ある消費行動の論文によると「超高関与を支える 知識や記憶を認知構造として捉え,超高関与の時の消費者による集中的な認知構造の形成によって,関与低下後もその分野の高度な認知枠組みとして機能すると考えた。」(堀田 2017)とあります。要は、買い物は体験を伴うと記憶に残り、記憶が薄れていってもその買い物の記憶は残りやすくなるということです。これは、「何を買うか」よりも「どうやってその商品を手に入れたか?」の体験のほうが大切だと意味しています。