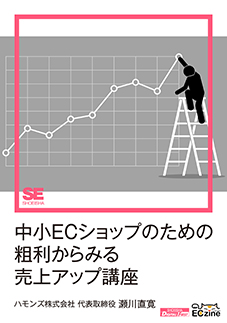会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
この記事は参考になりましたか?
- この記事の著者
-

ECzine編集部 木原 静香(キハラシズカ)
立教大学現代心理学部映像身体学科卒業後、広告制作会社、不動産情報サイトのコンテンツ編集、人材企業のオウンドメディア編集を経験し、2019年に翔泳社に入社。コマースビジネスに携わる方向けのウェブメディア「ECzine」の編集・企画・運営に携わる。2025年4月1日より、ECzine 副編集長を務める。
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事をシェア