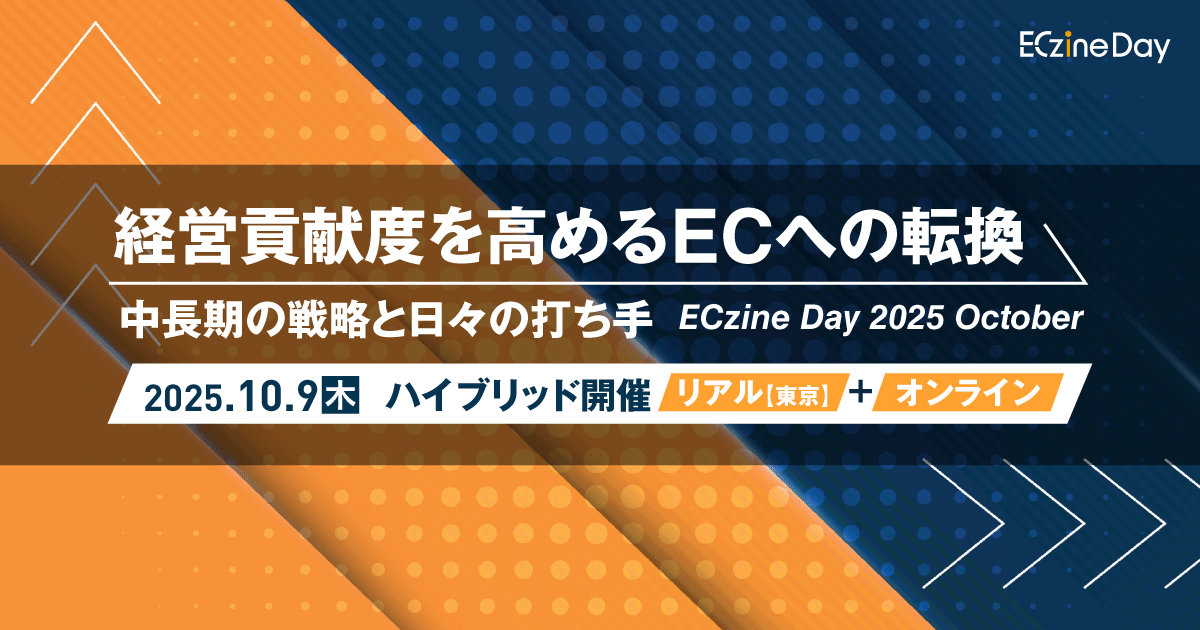顧客行動がブラックボックス化 その要因は?
2019年に、ミツカングループから誕生したD2Cブランド「ZENB」。グループミッション「やがて、いのちに変わるもの。」を体現するため、“美味しい”と“体に良い”を両立するパンや麺類といった主食を中心に販売している。自社ECサイトをメイン販路としながらも、近年はコンビニエンスストアやスーパーマーケットなど小売店にも進出し、顧客接点を拡大中だ。自社ECサイトにおけるビジネスモデルは、主にサブスクリプション。定期購入の割合は95%以上にものぼる。
そんな同プロジェクトに、立ち上げ時より携わっているのが、株式会社ZENB JAPAN ダイレクトチーム 部長の和田悠氏だ。同氏が登壇した事例セッションの冒頭で、ブランド運営において大切にしている考え方が語られた。
「当社グループの事業では、『相手の身になって考える』『前提条件を疑う』の二つを軸としています。つまり、顧客起点で仕事をするということです」(和田氏)
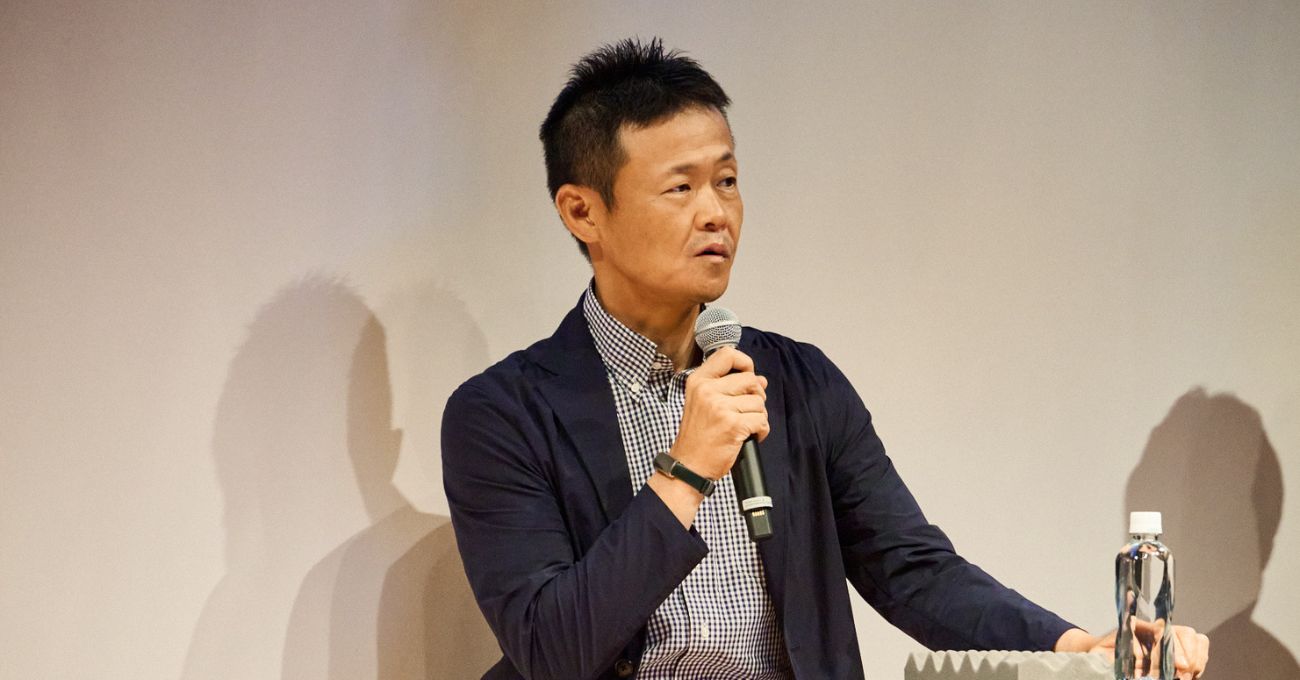
一方、それを実現する上でZENBには課題があったという。顧客理解の解像度だ。
「カスタマージャーニーを的確に把握するには、複数の定量・定性データをつなぎ合わせる必要があります。ところが、当初は実際にお客様がどのように自社ECサイトを利用したのか、クリック数、訪問率、売上、アンケート結果などのデータから推察するしかありませんでした。顧客行動が、ブラックボックス化している状態だったのです」(和田氏)
和田氏とともに登壇した株式会社DearOne グロースマーケティング部 アナリティクスユニット シニアコンサルタントの小島健一氏は、「仮に顧客行動を可視化するにも時間がかかる。データ分析の環境に課題を抱える企業は多い」と解説する。
こうした状況から脱却したい。そう考え、和田氏らが2025年1月より取り入れたのが、顧客体験を分析するためのプラットフォーム「Contentsquare」だ。同プラットフォームでは、顧客が実際に自社ECサイト内をどう遷移していったのかなど、具体的な行動を可視化できる。
「導入から約半年が経過し、自社ECサイトに訪れたお客様がなぜ商品の購入に至らなかったのか、少しずつ見えてきました。中には、カートに1度入れたにもかかわらず、離脱してしまう人もいます。何が起きたのか、なぜ起きたのかが把握できたことで、次の手立てが打てるようになりました」(和田氏)
Contentsquareでは、顧客行動を追体験できる様々な機能が活用できるという。ZENBでは、それらをどう組み合わせているのだろうか。和田氏は、成果が得られた改善施策について、話を進めた。
課題だった直帰率 顧客の迷いを特定できた施策とは
ZENBで主に活用されているContentsquareの機能は、次の三つだ。
講演内では、これらを通じた二つのユースケースが公開された。一つ目が、2025年7月に実施されたばかりの、自社ECサイトトップのリニューアル。改善前は、サイトトップに訪れた顧客の直帰率は約25%だった。このデータから「初めて訪問した人にとって導線がわかりづらいのではないか」と仮説を立てていたという。
「同年7月5日より、テレビCMが放送される予定でした。新規顧客の増加が見込まれていたため、その前に改善する必要がありました」(和田氏)
そこで、和田氏らがまず行ったのがContensquareのジャーニー分析だ。ここでは、次の図にもあるように、同じ色が同じページへの遷移を表している。

「ゼンブヌードルの紹介ページから、各商品の詳細ページへ、そしてまたゼンブヌードルの紹介ページへと戻っている人が多いことがわかりました。同じ色(ページ)を行ったり来たりしている。つまり、多くのお客様が自社ECサイト内で迷っているのです」(和田氏)
その上で、次に和田氏らが取り掛かったのがゾーニング分析。図のうち、左側が商品を買った人、右側が買わなかった人の閲覧状況となっている。和田氏は「ここでも、どのようなブランドなのかと、情報を探して迷っている様子がうかがえた」と話す。

リニューアル前のサイトトップには「スタートセット」「ブレッド」「ヌードル」「チップス」「商品一覧」と、複数の項目が並んでいた。顧客行動の分析後は、項目を減らしてシンプル化されている。顧客が直観的に求める情報にたどり着ける仕組みへと改善された。

もう一つのユースケースが、定期便ユーザーが商品の組み合わせを変えたり、スキップしたりするために必要なマイアカウントのアップデートだ。和田氏は「顧客満足度に特に貢献している部分。3ヵ月かけて大きく構成を変更した」と強調する。
まず、ジャーニー分析で行ったり来たりしている顧客が多いことから、不要な項目も表示されるハンバーガーメニューを削除。さらに、定期便の管理がしやすいように、送料無料を伝えるコンテンツも取り払い、何を注文しているのかファーストビューで目に入る仕様にしたという。加えて、ステップ1としておすすめ情報を表示し、ステップ2でレシピを提案することで、購入した商品の消費を促す工夫も行っている。

改善はこれで終わりではない。ZENBは、今後も継続的なデータ分析とアップデートで、顧客体験を向上し続ける考えだ。
「やればやるほど新たな課題が見えてきます。常にPDCAを回す必要があると実感しました。これからも、Contentsquareを通じて良い循環を作っていきます」(和田氏)
“同僚”のようにデータ分析をAIに相談 新たなインサイトを発見する方法
そんなZENBが活用しているContentsquareの価値を、より引き出す新機能が登場している。本イベントの基調講演では、ContentsquareのCEO 兼 創業者 Jonathan Cherki氏、Contentsquare Japanのシニア・ソリューションコンサルタント 沖本篤史氏より、さらに顧客体験の向上を加速させる方法も紹介された。
「顧客体験の向上を支える“高度な知能”になりたい」と力強く語るCherki氏。なぜ、Contentsquareに進化が必要だったのだろうか。
「当社が目指すのは、先を見越して考え、状況に適応し、問題を解決し、皆さんにかわって意思決定を行う存在です。そのために、コンテンツやカスタマージャーニー、収益、エラー、フィードバックなど、様々なデータを一つのプラットフォームで収集し、分析できる仕組みを提供してきました。一方で、市場は急速に変化していると同時に、顧客の企業への期待は高まっています。データ分析を再発明するタイミングではないでしょうか」(Cherki氏)

それを実現するのが、Contentsquareに搭載されたAI「Sense」だ。たとえば、自社ECサイトの購入率が下がっているとき、理由を探るためにSenseに「商品詳細ページからの決済への導線を確認したい」と質問すると、的確な回答を得られるという。


Senseが、商品詳細ページからカート、決済ページ、完了まで、顧客がどの程度遷移しているのかを読み取った上で、定量的な情報とともにサマリを表示する。さらに「決済ページの離脱が気になる」と質問すれば、Senseがジャーニー分析に切り替え、決済ページからカートに戻っている人の存在など、顧客行動の特徴を提示してくれるのだ。
Senseのデモンストレーションを行った沖本氏は、「何に着目して分析すれば良いかわからなくても、普段同僚にするような相談をSenseにできる」と話す。
「サイト内の課題を見つけるだけでなく、その改善インパクトまで提示します。『購入ボタンの配置をわかりやすくして導線を改善した場合、1ヵ月で600万円の売上成長が見込める』といった具合です」(沖本氏)

現在、Senseはさらなるアップデートを控えている。これまでは、ユーザーが「このページで離脱が多いから、もっと深掘りしてほしい」などと、一部の指示出しを行う必要があった。今後は、Senseが自ら自社ECサイトの構成を分析し、カートボタンの位置やクリック率、スクロール率などを把握。どこに改善点があるかを見つけた上で、対応策を迅速に提案できるようになる。
「Senseは、従来のアシスタントのような役割から一歩踏み込み、より自律的にデータを分析し、リアルタイムで改善の提案を行う“エージェント”へと進化していきます。分析したいページさえ入力するだけで、今まで気づかなかったインサイトや発見を自動的かつ定期的に受け取ることができるのです」(沖本氏)

このように、Contentsquareが目指すのは、AIが単なるツールにとどまらず、ビジネスの成長を後押しするパートナーとなる未来だ。講演の最後にCherki氏は、EC担当者・マーケターに向けてこうメッセージを送った。
「大きな変化は、ときに混乱をもたらすこともあるでしょう。しかし、私は新たなテクノロジーに対して、楽観的に捉えています。Senseが、皆さんにとって成長の機会を創造すると信じています」(Cherki氏)