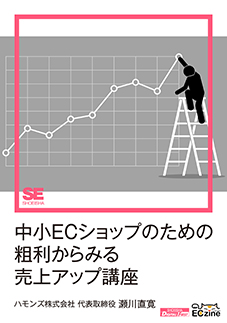ゆくゆくはサイトの流入に直接影響 表示速度1秒以内を目指し施策開始を
ここで、実際にIDOMが測定後に取り組んだ改善施策が紹介された。
施策を始めた2017年は、トップページの表示完了速度2秒以下を想定したものの、最速値の1パーセンタイルでもその基準値に届かず、60パーセンタイル以降に段差が生じる結果となっていた。それが2019年夏には、75パーセンタイルで2秒近い数値に抑えられ、2020年2月には78パーセンタイルで1秒以下の表示ができるようになったと言う。
さらに村田氏は、ページ遷移の動線で計測する3ページのトランザクション計測(メーカー→車種→車詳細)にも取り組んだ。2019年1月には、各ページで最速の1%でも基準値である表示完了1秒に達していなかったが、1年経った現在は各ページで98%が基準値内に収まり、表示完了は1.5秒から0.6秒に削減された。加えて、高速化の施策の効果がサイト全体に波及して、サイト全体の平均読込時間が短くなった。Google Analyticsのデータでは、コンバージョンに至ったページは、コンバージョンできなかったページより高速であることが判明している。

こうした効果を得るための具体的な施策について、村田氏は「環境はすべてのサイトで異なるので、用法・容量に注意」と前置きしながら、リクエスト開始からレスポンスまでに行った内容を紹介した。「手を付ける順番や環境によって、大きな差が出ることがあるため、ぜひとも主治医の監督のもとで行ってほしい」と述べたうえで、IDOMでは「レンダリングの際にブロッキングが発生しないようにすること(=Rendering Friendly)」に現在取り組んでいると語った。
また、速度を上げるなら「優先度の低いものは大胆に削る」のもひとつの手と続けた。コントロールできるファーストパーティから手を付け、削る場合は自身でコントロールできないサードパーティタグを避けるのがおすすめだと言う。
村田氏はここで改めて初速にこだわる理由を述べた。「たとえば、ABテストの影響範囲は部分的だが、速さはウェブサイト全体にかかわってくる。それを最適化しない手はないのではないか」としたうえで、Jacob Nielsen氏が説く「Powers of 10(10の累乗)」を紹介した。ウェブサイトに対する第一印象が形成されるのは0.1秒。1秒は自分の考えに集中したままでいられるが、10秒を超えれば去っていく。つまり、UI操作の応答は0.1秒以内、ページロードは1秒以内、画面の操作に必要な時間は10秒以内が望ましいということだ。
また、2020年よりGoogleの評価が変わることが予想されている点にも村田氏は言及。2019年まではFCPやDOM Content Loaded、Onloadが重視され、ビジネスに影響のある部分を速くすることが重要とされていたが、今後はスループットよりレスポンス優先で、初速が重視されると見られている。
ここで興味深いのが、表示速度に対するユーザーの行動だ。2019年12月度に行われたジャストシステムの調査によると、スマホECで離脱した平均的な秒数は3秒未満が18%、3秒以上となると82%に上ると言う。
さらに、「市場環境からもサイト速度の向上が必須となってきた」と村田氏は続ける。その理由のひとつは、5G時代の到来だ。5Gが普及することで、回線以外の品質の差が大きく現れることになる。
村田氏は、「2021年からは、もう『回線が遅い』と言えない。キャリアもデバイスも速くなり、ミドルやバックエンドのボトルネックが露わになる」と警鐘を鳴らしたうえで、2019年11月にChromiumから発表されたラベリングについて触れた。これにより、低速のラベリングがされたサイトはユーザーの直帰率が上がり、検索順位も流入も下がる可能性が高くなる。

最後に村田氏は「まだ幸い1年ある。できれば1秒、最低2.5秒以内にするために施策を開始しよう」と呼びかけたうえで、「2019年より、トレンドはパーソナライゼーションからローカリゼーションにシフトしつつある。スマホ検索の3分の1は来店直前に行われ、消費者の43%が店舗にいる間もオンライン調査をしている今、購入決定の直前までコンテンツの提供・表示を諦めてはならない。そのためにもぜひとも速度改善に取り組んでほしい」と語り、セッションを締めくくった。