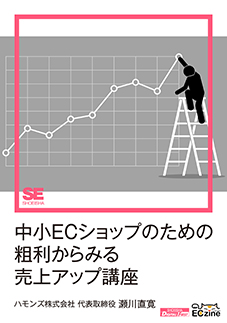ウェブパフォーマンス向上でコスト削減 表示速度改善がもたらす効果とは

年間の商談件数60万件、小売12万台を誇る中古車販売サービス「ガリバー」。運営事業者であるIDOMでは、20年前からウェブサイトをリアル店舗への集客・送客装置のひとつとして活用してきた。
IDOMが身を置く自動車業界は、現在100年に一度の大変革期と言われている。IDOMでも、サブスクリプションモデルやカーシェアリング、CtoC向けサービスなど新しい取り組みを行っており、さらに従来から存在する店舗を中心とした中古車販売モデル(CtoBtoC)についても、新たな戦略が求められている。
そうした中、同社は顧客とのタッチポイントのひとつとして重要な役割を担うウェブサイトについても、顧客体験向上を目指し、3年間にわたってウェブパフォーマンス改善を実施してきた。いわゆる「速度の向上」に取り組むことで、想像以上の効果が得られたと言う。流入は3年間で約2倍に増え、リードの獲得割合も2年めに15%向上している。さらに注目すべきは、2019年に25%の運用費削減に成功していることだ。
「私たちのビジネスモデルはウェブ上で購買が完結するのではなく、成約までに数回、人の介在が必要になる。そのため、コスト配分においてウェブサイトよりもリアルの比率を高めることは必然的な判断だった。ただし、コストは減らしても効果は下げない。その課題のもと、取り組みを進めた結果、費用対効果を高めることができた」と村田氏は説明した。
そして定性効果については、速度改善によって表示品質が安定し、クロールやインデックスが進むようになったことを挙げた。エラーが減ってクロールバジェットに余裕ができたことで、ページのインデックス量が増加。かつて減らしていたサイトマップも2019年秋頃に復活させ、「コンテンツが増えてもうまくデリバリーができるようになってきた」と言う。
こうした成果を得るまでに、IDOMではどのような施策にどの程度の力を注いだのだろうか。村田氏は、「最初の2年間はEFO(フォーム最適化)やLPO(ランディングページ最適化)などに注力したが、近年はチャット接客やウェブ接客などに移行している」と施策を振り返った。さらに「併行して、パフォーマンス速度改善という目に見えない領域にも注力するようになった。それが、目に見える領域にも大きく影響することを実感した」と語る。
効果的にサイトの品質改善がかなえば、余剰となった人力やコストを戦略的に他に回すことができる。同社では、コンテンツが量から質へとシフトし、Googleを活用した効果的なデリバリーを行えるようになったそうだ。これにより広告出稿量の適正化などを実現し、削減できたコストは新たな顧客接点の開発・運営費用や、店舗に直送する仕組みの構築、データオーケストレーションなどの新施策に展開している。
また、サイト品質改善が施策成果につながるということは、裏を返せば表示速度が遅いと効果発現が削がれるということでもある。村田氏も取り組みの中で「表示速度が遅い状態では、EFOやLPOの成果は十分に得られなかった」と言う。しかし、たとえばECでカゴ落ちするユーザーが多かった際に、その原因が表示速度にあるとは気づきにくい。気づくことができないからこそ、表示速度改善は常に意識すべき事項と言えるだろう。
トップサイトに見るパフォーマンスの重要性 必要なのは「主治医」を見つけること
表示速度が速くなるメリットとは何だろうか。SimilarWebが発表する「世界の上位ウェブサイトランキング」と、Chromeユーザーのパフォーマンスデータを分析した「CrUX(Chrome User Experience Report)」を見ることで、新たな視点を得ることができる。2019年6月に調査された前者のレポートによると、月間のトラフィックの総量はアメリカのGoogle(google.com)が1位となっており、YouTube(youtube.com)やFacebook(facebook.com)が後に続く。日本のウェブサイトでは、22位にYahoo! JAPAN(yahoo.co.jp)が入り、NTTドコモ(docomo.ne.jp)やAmazon(amazon.co.jp)などが100位に入っている。

CrUXによると、これら日本のサイトはほとんど4Gで閲覧されている。ページ内のテキストやグラフィックが表示される速さ(FCP:First Contentful Paint)の9割は平均以上であり、反応遅れ(FID:First Input Delay)も決して多くはない。しかし、表示完了時間を表すDOM Content Loadedや処理開始時間を表すOnloadは、広告計測タグなどの影響もあるのか、サイトごとに品質の差が生じている。


ここから読めることは、ふたつある。日本のサイトは、初速は速いが読み込みがやや劣るということ、そしてUXにしっかり取り組んでいるサイトはDelay(遅延)が少ないということだ。
上位サイトのように快適なウェブパフォーマンスを実現するにはどうしたらいいのか。一般的なベストプラクティスとして、HTTP/2やAMP、Googleタグマネージャー(GTM)、画像圧縮、LazyLoadや非同期処理のような読込遅延などのキーワードがよく聞かれる。IDOMでも、これらほぼすべてに手をつけたが、いずれもうまくいかなかったと言う。ここで村田氏は、ウェブパフォーマンス改善の際に検索キーワードで使う言葉が日本と海外で違うことを述べた。
「検索クエリを見ると、皆さん『Pagespeed Insights』や『Webpagetest』と検索しているようだが、本格的な改善を目指すなら、本来は『ウェブパフォーマンス』という視点に基づく必要がある。技術分野を調べる際に、検索キーワードを間違えてしまうというマーケターが陥りがちな傾向であり、エンジニアなら躊躇なく『ウェブパフォーマンス』と調べるはずです」(村田氏)
また、村田氏は「CrUXだけで打ち手を決めるのは危険」と続け、その理由として、CrUXの調査対象がChromeユーザーのみであることを挙げた。日本は、世界でも稀に見るApple優勢国であり、Safariユーザーが4割を占めている。そのような状況を踏まえ、「全体を見て考えないと、方向性を誤る可能性もある。『どうやるか』はもちろんだが、『誰と一緒にやるか』まで考え、全体を俯瞰できる人と組む必要があるだろう」と、パートナーの重要性を語った。
しかし、多くの企業ではインフラ構築からウェブコンテンツの制作まで、さまざまなベンダーと組んでいるはずだ。ウェブサイトの上流から一気通貫で診断を行うのは、なかなか困難とも言える。実際のところ、IDOMでもパフォーマンス改善の「主治医探し」に困っていた中でSpelldataと出会い、施策をスムーズに進められるようになったと言う。
パフォーマンス改善にあたり苦労した点として、村田氏は主治医探しの他にも改善体制の構築や施策の負荷軽減などを挙げ、「サイト運用は常に規律が必要」と強調した。
まずは「ウェブパフォーマンスの見える化」から 目を背けず現実と向き合おう
それでは実際に、どのようにして速度改善に取り組んでいけばいいのか。まず行うべきは、「ウェブパフォーマンスの見える化」だと言う。
ここで村田氏は、2010年に行われた「Google Developer Day 2010 Japan」で披露された「Don't Guess! Measure!(推測するな!計測せよ!)」という言葉を引用した。そして、「測定結果からボトルネックを特定し修正するという原則は、10年前から変わっていない」と語ったうえで、こう続けた。
「測定して十分に高速であれば、その施策は完了とすることができます。アメリカでは、1秒以内で表示完了できれば十分と言えるレベルであり、日本では3秒と言われているが、今後は日本もアメリカレベルを指標にすべきです」(村田氏)

また、ウェブパフォーマンス業界に伝わる「エンドユーザーに対するレスポンスタイムのうち、80~90%はウェブフロントエンドで発生している」という言葉に対し、村田氏は「実際には、ウェブサイトやビジネスによって異なるのではないか」と疑問を呈した。IDOMの場合、フロント領域がボトルネックになっているケースは、半数ほどだと言う。
さらに、パフォーマンス向上のための指標として、速度計測をウォーターフォールで表したものがあるが、それについても村田氏は「その場限りの計測で、瞬間最高速でしかない可能性が高い。他の時間や状況で異なる可能性もあり、真のボトルネックを見出しにくい」と評した。
「IDOMでは、Spelldata が提供する『Catchpoint』で15分に1回測定する累積分布関数のグラフを用いました。改善は歪みを正し、高いところを抑制していく。24時間365日、可能な限り同じ水準でサービスを提供することが目的ゆえ、理にかなっています」(村田氏)


※品質管理上、ウェブパフォーマンスや通信速度は左右非対称分布となるため、標準偏差ではなく、パーセンタイルを使うのが一般的である。15分に1回の頻度で計測することで、1ヵ月あたり2,880回の観測値となり、それらの観測値を累積分布関数を使い、速い順に並べることで1ヵ月あたりの配信品質を確認することができる。1パーセンタイルは1ヵ月の観測値で最も速かった値、100パーセンタイルが最も遅かった値となる。98パーセンタイルで1秒以内とは、1ヵ月あたり98%の確率で、1秒以内に表示完了を経験するという意味になる。
Catchpointでは接続環境の違いごとに測定した分布図を作成することもできる。場所によってのパフォーマンスのばらつきをなくすためだ。
村田氏は、「見える化すると、目を背けたくなるような数字がたくさん出てくる。残酷かもしれないが、そこから直せることはきっとある」とまずは測定から始めることを勧めた。
ゆくゆくはサイトの流入に直接影響 表示速度1秒以内を目指し施策開始を
ここで、実際にIDOMが測定後に取り組んだ改善施策が紹介された。
施策を始めた2017年は、トップページの表示完了速度2秒以下を想定したものの、最速値の1パーセンタイルでもその基準値に届かず、60パーセンタイル以降に段差が生じる結果となっていた。それが2019年夏には、75パーセンタイルで2秒近い数値に抑えられ、2020年2月には78パーセンタイルで1秒以下の表示ができるようになったと言う。
さらに村田氏は、ページ遷移の動線で計測する3ページのトランザクション計測(メーカー→車種→車詳細)にも取り組んだ。2019年1月には、各ページで最速の1%でも基準値である表示完了1秒に達していなかったが、1年経った現在は各ページで98%が基準値内に収まり、表示完了は1.5秒から0.6秒に削減された。加えて、高速化の施策の効果がサイト全体に波及して、サイト全体の平均読込時間が短くなった。Google Analyticsのデータでは、コンバージョンに至ったページは、コンバージョンできなかったページより高速であることが判明している。

こうした効果を得るための具体的な施策について、村田氏は「環境はすべてのサイトで異なるので、用法・容量に注意」と前置きしながら、リクエスト開始からレスポンスまでに行った内容を紹介した。「手を付ける順番や環境によって、大きな差が出ることがあるため、ぜひとも主治医の監督のもとで行ってほしい」と述べたうえで、IDOMでは「レンダリングの際にブロッキングが発生しないようにすること(=Rendering Friendly)」に現在取り組んでいると語った。
また、速度を上げるなら「優先度の低いものは大胆に削る」のもひとつの手と続けた。コントロールできるファーストパーティから手を付け、削る場合は自身でコントロールできないサードパーティタグを避けるのがおすすめだと言う。
村田氏はここで改めて初速にこだわる理由を述べた。「たとえば、ABテストの影響範囲は部分的だが、速さはウェブサイト全体にかかわってくる。それを最適化しない手はないのではないか」としたうえで、Jacob Nielsen氏が説く「Powers of 10(10の累乗)」を紹介した。ウェブサイトに対する第一印象が形成されるのは0.1秒。1秒は自分の考えに集中したままでいられるが、10秒を超えれば去っていく。つまり、UI操作の応答は0.1秒以内、ページロードは1秒以内、画面の操作に必要な時間は10秒以内が望ましいということだ。
また、2020年よりGoogleの評価が変わることが予想されている点にも村田氏は言及。2019年まではFCPやDOM Content Loaded、Onloadが重視され、ビジネスに影響のある部分を速くすることが重要とされていたが、今後はスループットよりレスポンス優先で、初速が重視されると見られている。
ここで興味深いのが、表示速度に対するユーザーの行動だ。2019年12月度に行われたジャストシステムの調査によると、スマホECで離脱した平均的な秒数は3秒未満が18%、3秒以上となると82%に上ると言う。
さらに、「市場環境からもサイト速度の向上が必須となってきた」と村田氏は続ける。その理由のひとつは、5G時代の到来だ。5Gが普及することで、回線以外の品質の差が大きく現れることになる。
村田氏は、「2021年からは、もう『回線が遅い』と言えない。キャリアもデバイスも速くなり、ミドルやバックエンドのボトルネックが露わになる」と警鐘を鳴らしたうえで、2019年11月にChromiumから発表されたラベリングについて触れた。これにより、低速のラベリングがされたサイトはユーザーの直帰率が上がり、検索順位も流入も下がる可能性が高くなる。

最後に村田氏は「まだ幸い1年ある。できれば1秒、最低2.5秒以内にするために施策を開始しよう」と呼びかけたうえで、「2019年より、トレンドはパーソナライゼーションからローカリゼーションにシフトしつつある。スマホ検索の3分の1は来店直前に行われ、消費者の43%が店舗にいる間もオンライン調査をしている今、購入決定の直前までコンテンツの提供・表示を諦めてはならない。そのためにもぜひとも速度改善に取り組んでほしい」と語り、セッションを締めくくった。