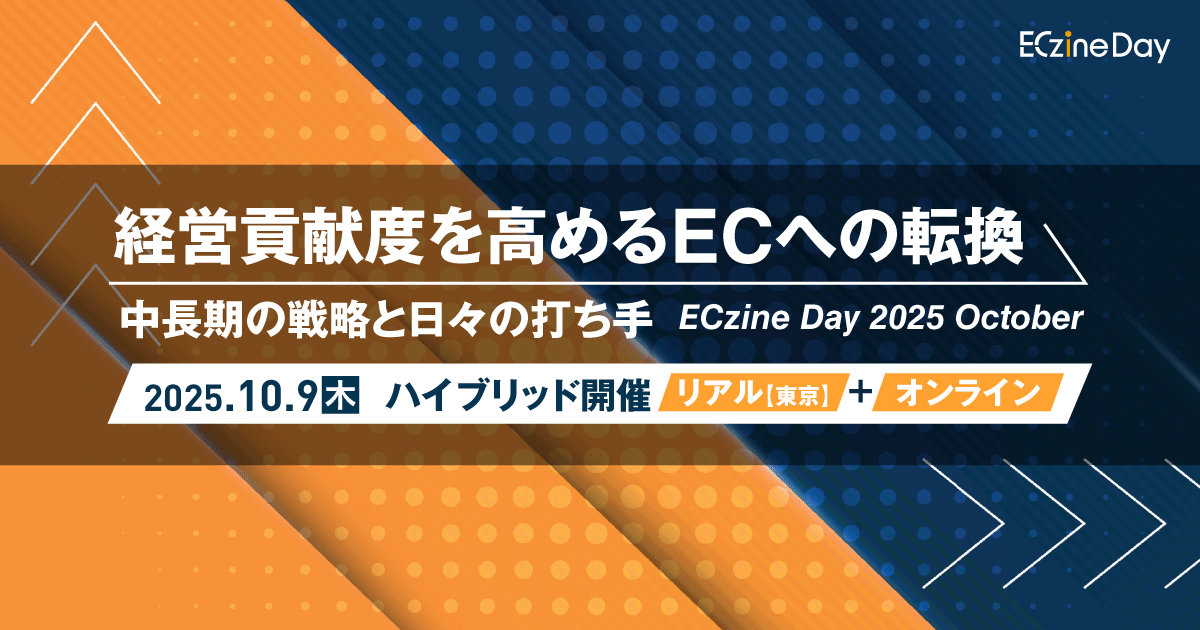会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
この記事は参考になりましたか?
- EC業務に変革をもたらすAI 共存の先に見えるものとは連載記事一覧
-
- AI時代の中小ECは「ハックする」より「誠実さ」で勝ち抜こう[河野貴伸氏×運営堂 森野氏対...
- 「みんなの1位」から「あなたに最適」へ AIが変えるECの未来[河野貴伸氏×運営堂 森野氏...
- AI導入を妨げる小さな誤解 セールスフォース「Commerce Cloud」GMが最新動向...
- この記事の著者
-

森野 誠之(モリノ セイジ)
運営堂代表。Web制作の営業など数社を経て2006年に独立後、名古屋を中心に地方のWeb運用を支援する業務に取り組む。現在はGoogleアナリティクスなどのアクセス解析を活用したサイト・広告改善支援を中心にWeb制作会社と提携し、分析から制作まで一貫してのサービスも開始。豊富な社会・業務経験と、独立系コンサ...
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事をシェア
![AI時代の中小ECは「ハックする」より「誠実さ」で勝ち抜こう[河野貴伸氏×運営堂 森野氏対談後編] (3/4)|ECzine(イーシージン)](http://eczine-cdn.shoeisha.jp/static/templates/img/common/logo_eczine.svg)

![AI時代の中小ECは「ハックする」より「誠実さ」で勝ち抜こう[河野貴伸氏×運営堂 森野氏対談後編] (3/4)|ECzine(イーシージン)](http://eczine-cdn.shoeisha.jp/static/templates/img/common/logo_eczine_h.svg)