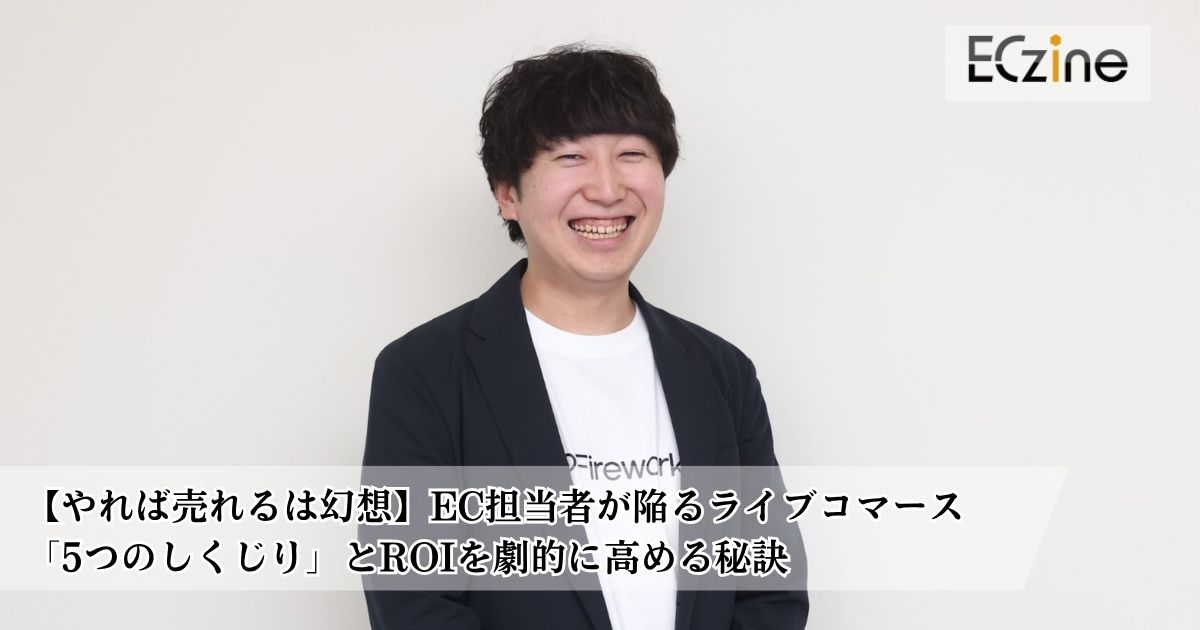日本におけるライブコマースの“最初の壁”とは?
大里 ライブコマースのしくじりから学ぶ本連載、2回目となる今回はライブコマースに黎明期から携わっている石島さんに、ライブコマースで起こりがちな“しくじり”と対応策についてうかがいます。
まず2016年頃に、中国のライブコマースが急成長したタイミングがあったと思います。その影響は日本にもあったのでしょうか?
石島 間違いなくあったと言えると思います。当時はアリババ傘下のタオバオやJD.comといった大手ECで、配信をきっかけに数十億円が動く“爆売れ現象”が日常的に起きていました。人気インフルエンサーは1回の配信で数十億円を売り上げ、「配信=即購入」という文化が一気に広がりました。
「中国で成功しているなら日本でも」と、大手企業が相次いで参入しましたが、多くが失敗に終わってしまい、国内市場では盛り上がりませんでした。

新卒でテレビ番組制作会社に入社し、バラエティ番組を担当。2015年に動画ベンチャーに転職し、LINE LIVEやAbemaTVなど、ライブ配信が盛り上がり始めた時期にプロデューサーとして番組制作や企画に携わる。2017年には自社アプリを使ったライブコマース事業の立ち上げも経験。その後、大手音楽レーベルでアーティストのYouTubeチャンネル立ち上げや運用、スタートアップでの企業YouTube運営などを経て、現在はFireworkで動画マーケティング全般の支援を行っている。
大里 国内市場でうまくいかなかったのには、どのような理由があったのでしょう?
石島 大きく3つの理由があります。1つ目は、中国のやり方をそのまま持ち込んだこと。配信中に80%オフなどの大幅値引きや、KOLと呼ばれるインフルエンサー依存の手法は、日本の商習慣には馴染みませんでした。
2つ目は、外部の有名人頼みでコストが高騰し、継続できなかったこと。当時は今では主流となっている「社員の方が出演する」というスタイルの配信がほとんどなく、インフルエンサーなど外部頼みにならざるを得ませんでした。
3つ目は、決済や購買データのインフラが未整備だったこと。当時の日本ではまだPayPayすら存在せず、オンラインにおけるスムーズな購買体験を提供できなかったのはもちろん、ライブ配信経由の購買をトラッキングすることが非常に難しかったのです。
日本では「配信を見て店舗で購入」という行動も多く、そこが計測できないためROIが可視化できず撤退する企業が相次ぎました。