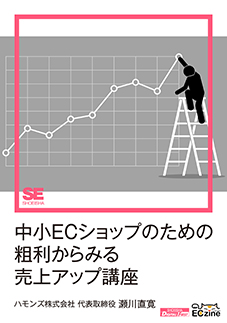時代の波に乗るだけでは成功しない D2Cの醍醐味とは
磯山 D2Cビジネスを成長させるには、顧客の声を基に商品やサービスを磨き込むことが欠かせませんよね。ECHさんも新商品の開発や既存商品のアップデートをかける際にさまざまな顧客の声に耳を傾けているかと思いますが、ヒットを生む秘訣はどこにあるのでしょうか。
井関 D2Cブランドがヒットを生み出すのは、本当に難しいことです。「運」の要素もないとは言い切れないでしょう。「KAMIKA」の場合、立ち上がりから順調にブランドが成長した理由のひとつに、スマートフォンの普及があります。
「KAMIKA」は、40代から60代の女性を主なターゲットとしたヘアケアブランドです。ブランドが生まれた2018年頃から、iPhoneをはじめとするスマートフォンの利用者層が広がり、多くの人々がコミュニケーションの手段としてLINEを活用するようになりました。ここからコロナ禍にかけてEC利用も広がってきたわけですが、当時この世代をターゲットにし、積極的に商品開発やマーケティング訴求に投資するヘアケアブランドがそこまでいない状況だったのです。こうした空白地帯をチャンスと考え、当社は広告施策を実施。認知獲得に注力したことで多くの新規顧客を獲得することに成功しました。
磯山 商品、マーケティング、カスタマーサポートの体制を整えた上で、うまく時代の波に乗れた、ということでしょうか。

井関 時代の波に乗るだけでは成功しませんし、そもそも波を見つけてから取り組んでも、すでに先駆者がいるはずです。乗り遅れないために、ECHでは定期的に1,000人から2,000人規模の顧客アンケートを実施しています。「今後欲しい商品」や「商品を実際に使ってみて感じたこと」などを聞くことで、顧客が今求めるものや時代の流れが見えてくるので、今後の指針となります。
磯山 生の声が直接、商品やマーケティングに活かされているのですね。
井関 従来型のメーカーは、商品を開発して世に出すまでが勝負で、開発者が商品を手に取った顧客の声を聞きたいと思っても、なかなか実行しづらいのが実情でしょう。その点、ECHはメール、LINE、電話など顧客とコンタクトできる手段をさまざま持っているため、商品の発売後も直接意見をいただき、商品改良や訴求内容の磨き込みなどに活かしています。
磯山 ECHさんに直接意見を寄せてくれるほどファン度が高い顧客の声を、どう商品やビジネスに組み込むか。こうした課題と向き合えるのはD2Cのおもしろさですが、大変な部分もあるのではないでしょうか。
井関 「商品そのものを変える」となると時間が必要です。そのため、商品ラインナップの拡充や改良など取り組めるところから順次顧客に見える形でフィードバックをするようにしています。
たとえば「KAMIKA」では、「ヘアオイルが欲しい」という声に応えて商品開発を行いました。また、アンケート聴取した顧客の3割が「もっと環境面に配慮したい」と回答していたことを踏まえ、詰替パックの容器や配送時の梱包素材を変更しています。このように新商品の開発だけでなく、事業のさまざまな部分に顧客の声を反映している点は、D2Cらしさと言えると思います。
磯山 当社も「KAMIKA」の立ち上げ初期から、「BOTCHAN」の提供を通してコミュニケーションしてきましたが、ECHさんは外部パートナーとの関係構築も大事にされている印象です。何か意識していることはありますか?
井関 「自分たちだけで完結するビジネスではない」ということを常日頃忘れないように意識していますね。事業を成長に導くには、社員も外部パートナーも目線を合わせ、共通の目標・ゴールに向かって前進できる組織作りが欠かせません。
トップダウンで物事を動かす、いわば「恐怖政治」が通用する時代ではないですし、私自身も経営者としてこうした組織運営をしたいと思っていません。ECHは「ECを通じて感動をお届けする」をビジョンとして掲げていますので、かかわる全員が主体的にビジョンに向かって突き進むことができるチーム作りが大切だと考えています。
磯山 かかわる全員が、ビジネスを自分ごと化できるようにする。これは非常に重要ですね。
井関 1人ひとりがビジネスの目的を理解し、主体的に動けるようになると、アウトプットも成果も変わります。ビジネスを営む限り、貸借対照表や損益計算書といった数字への意識も大事ですが、現場レベルでは「このブランドのために一緒に仕事をしたい」といった思いや自己実現、日々のやりがいを感じられるかどうかが向上心を大きく左右します。良質なチームビルディングを実現するには、こうした日々の積み重ねに手を抜いてはいけません。
私は、すべてのブランドを「短命で一時稼いで終わる」という形にしたくないと考えています。せっかくの人生で後世に残らないものを作っても意味がないですし、こうしたブランド運営は何より顧客や一緒に働いてくれる社員、外部パートナーに失礼だと思っているからです。「三方よし」で永続するブランド作りを、今後も目指していきます。