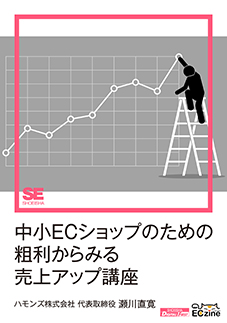急拡大するD2C 背景にあるのはデジタルトランスフォーメーション

2014年12月に創業したSUPER STUDIOは、「ECをアップデートし、人々に新しい体験を提供」をミッションに、テクノロジーを駆使したEC基幹システム「EC Force」と、D2Cに関するコンサルティングサービス「Apollo D2C」を提供している。同社はこれらふたつのサービスを「D2C as a Service」と総称しており、真野氏は「D2Cに特化してテクノロジーとコンサルティングの双方を提供できるのは、国内で当社だけ」と説明した。
同社の視点からD2Cというビジネスモデルを見ると、「これまでは製造から卸、販売まで分断され、顧客との接点もバラバラであった従来の販売形態とは異なり、一気通貫で統合している点に価値がある」と真野氏は続ける。
D2Cが流行している理由について、真野氏は「スマートフォンの普及によって、インターネットへのアクセス時間が増加した点、そしてSNSの爆発的な広がりによって、一方的な情報発信から相互発信に変わってきた点がある」と語り、さらに「SNSのシェアによって、ユーザーが良いと評価したものは積極的に広がるため、企業は『シェアされる情報』を把握することが求められるようになった」と分析する。
また、「サブスクリプションビジネスの台頭もD2Cの広がりのひとつの要因である」と真野氏は続けた。日本でサブスクリプションビジネスと言うと、「Netflix」や「Spotify」など動画や音楽の配信サービスに活用される印象が強いが、現在ではD2Cにおいても同形態をとるサービスが急増している。サブスクリプションビジネスは、従来型のビジネスで分断されていた情報を顧客起点でつなげ、顧客の意見を踏まえながら常に商品を進化させていく必要がある。これは一気通貫でサービス提供を行うD2Cのビジネスモデルとも相性が良く、互いに相乗効果をもたらしていると言っても過言ではない。
さらに近年、D2Cのスタートアップが大手企業に買収される事案が増えている。ユニリーバやプロテクター・アンド・ギャンブル(P&G)といったグローバル企業から、ワコールホールディングスや資生堂などの国内企業まで、さまざまな企業がD2Cに注目している状況だが、この傾向は、スタートアップ企業にとっては大きなチャンスとも言える。たとえば、ユニリーバが買収したシェービングブランド「Dollar Shave Club」は、ひげ剃りの替刃を定期購入できるサブスクリプションモデルで、当時の売上規模約220億円に対し、その5倍となる1,100億円で買収されている。こうした事例からも、D2Cが行うサブスクリプションビジネスに対する市場からの期待度の高さが想像できるだろう。
D2Cビジネスが注目される大きな理由には、顧客との対話性に加え、顧客データを把握しデータドリブンなビジネス構築が可能となる点がある。それはすなわち、「デジタルトランスフォーメーション(DX)化」であり、顧客データやデジタルツール活用の重要性が認められているからこそ、大企業もD2Cビジネスの動向を注視している状況だ。SUPER STUDIOでは、D2Cの定義について「デジタル化によって変化した消費行動に最適なマーケティングフレームワークのひとつ」と位置づけている。真野氏は、「これらを実践することで、今の時代に合った商品作り、お客様に合ったプロダクト開発がしやすくなる」と伝えた。
D2Cの成功に欠かせぬCVR向上 必須の取り組み3点を事例とともに紹介
D2Cをマーケティングフレームワークのひとつととらえた場合、「D2Cらしくないマーケティング」とはどのようなものなのだろうか。真野氏は「自社でデータを取得できない」「データドリブンではない」「体験作りができない」の3点を挙げ、「システム起因でこのようなことが起きてはならない。そのためにはどうしたらいいのかを考えることが重要」と語る。
D2Cビジネスを成功に導くには、CVR向上は必須事項だ。CVRが上がるということは、つまり「お客様に届く」ということである。真野氏は、お客様に商品を届けるために注力すべき3点について、事例を交えながら紹介した。
まずひとつめは、「顧客の共感・安心感を得ること」。事業への思いやブランドのストーリーに共感した顧客を獲得し、驚異的な継続率を実現したり、InstagramなどSNSを活用して顧客とコミュニケーションをとりながら意見や反応を商品開発に活かしている企業もある。
ふたつめは、「流入経路別に顧客の熱量の推測、およびクリエイティブのテストを繰り返し行うこと」だ。ウェブ広告などの施策を指名キーワード別やSNSの流入経路別、季節別などでテストを繰り返し行っている男性化粧品メーカーの「バルクオム」。同社は適したクリエイティブを探ることで地道に成果を上げている。
そして、3つめは「購入の過程でお客様に『体験』を与えること」。パーソナライズサプリメントを開発・販売する「トリコ」では、肌診断を行い、その人に合った処方のサプリメントが選定されるという体験を提供している。また、体験については購入したものが手元に届く瞬間にどのような体験提供を行うかも非常に重要なポイントだ。トリコもバルクオムも、届いた瞬間の感動を演出するべく、パッケージには工夫を凝らしていると言う。
真野氏は、「好調なD2Cはこうした施策を地道に行っているからこそ、CVRを上げ、多くのお客様に商品を届けることができている。これらはD2Cだからこそできることでもあり、皆さんにもぜひとも実践してほしい」と語った。
基幹システム提供だけでなく製品開発も伴走 SUPER STUDIOのD2Cビジネス支援とは
EC基幹システム「EC Force」とコンサルティングサービス「Apollo D2C」でD2Cビジネスを支えるSUPER STUDIO。真野氏はApollo D2Cについて、「ビッグデータの分析によって、どんな商品が売れるのか、どこでつまずくかまで分析・サポートしている。一般的な『口出しするだけ』のコンサルティングではなく、一緒に手を動かしグロースまでサポートを行うのが特徴だ」と強調した。
Apollo D2Cでは、さまざまな課題を事業ごとのフェーズに分類し、それぞれに対する解決策を提案していると言う。まず検討フェーズでは、「D2Cに取り組みたいが、何をしたら良いかわからない」という相談から、投資金額や利益額の予測まで、事業の立ち上げに関するサポートを行っている。準備フェーズでは、OEM先の選定や見落としがちなロジスティクス、カスタマーサポートの構築などもニーズに合わせて提案するが、「とくに相談内容として多いのは、マーケティングの戦略立案・準備に関するもの」だと真野氏は語る。手法が多様化し規制もある中で、最適な手法選定・実践まで併走するのがApollo D2Cの特徴だ。また、創業フェーズからスケールフェーズについては、クリエイティブやシステムの変更提案といった支援を行っている。

SUPER STUDIOは、こうしたノウハウを活かし、さまざまな企業とタッグを組むことで多くの成果を上げている。ベクトルとは合弁会社スリーズを立ち上げ、ベクトルが持つPR力とSUPER STUDIOのD2Cに関するノウハウを活かした商品開発・販売を行い、まつげ美容液などで成功を収めている。
なお、EC Forceはもともと化粧品メーカーとして同社が事業を展開しようとした際に、現場の課題を解決するために開発されたのが製品としての始まりだと言う。サブスクリプションに取り組みやすい管理機能や決済連携、ウェブ広告運用やCVR向上、物流をシームレスに進めるための管理機能など、D2C特化の基幹システムとして機能を取り揃えている。月平均20~30のアップデートを繰り返し、常により良いサービスを提供すべくまい進している。リリースから3年で累計250ショップが採用していて、1ショップあたりの平均年商は2億円になる。
また、1ショップあたり平均6名以上で手厚くサポートを行っていることもEC Forceの大きな優位性と言えるだろう。真野氏は「D2Cに必要な要素を全て兼ね備えたカートシステム」と語り、「『顧客体験の最大化』を掲げ、EC Forceへのカート移行後のCVRアップ率は平均400%超となっている」と強調した。

EC Force利用者は、スタートアップのD2Cブランドはもちろんのこと、最近では何かしらの課題を抱え他社カートシステムから移行するメーカーも増えているという。真野氏は、バルクオムがEC Force導入を決めた理由について「ブランドを打ち出すため、デザインにおける自由度が最重要だった」という同社 代表取締役 CEO 野口卓也氏のコメントを引用した上で、「他にも、サブスクリプションや広告戦略など同社が叶えたい施策に対し、システムがボトルネックにならない点も評価された」と分析した。同社はEC Forceへのカート移行により、売上が7倍にも増加したと言う。
最後に真野氏は、SUPER STUDIOの優位性について「D2Cに必要な要素を全て備えた高付加価値カートシステムを持ちながらも、ツール提供に留まらない、D2C事業を成功に導くコンサルティング力がある。さらにD2Cメーカーにノウハウ提供する各種イベントやEC Forceのクライアント向けのセミナー、Meet upを随時開催し、最新のノウハウを共有している」と語った。