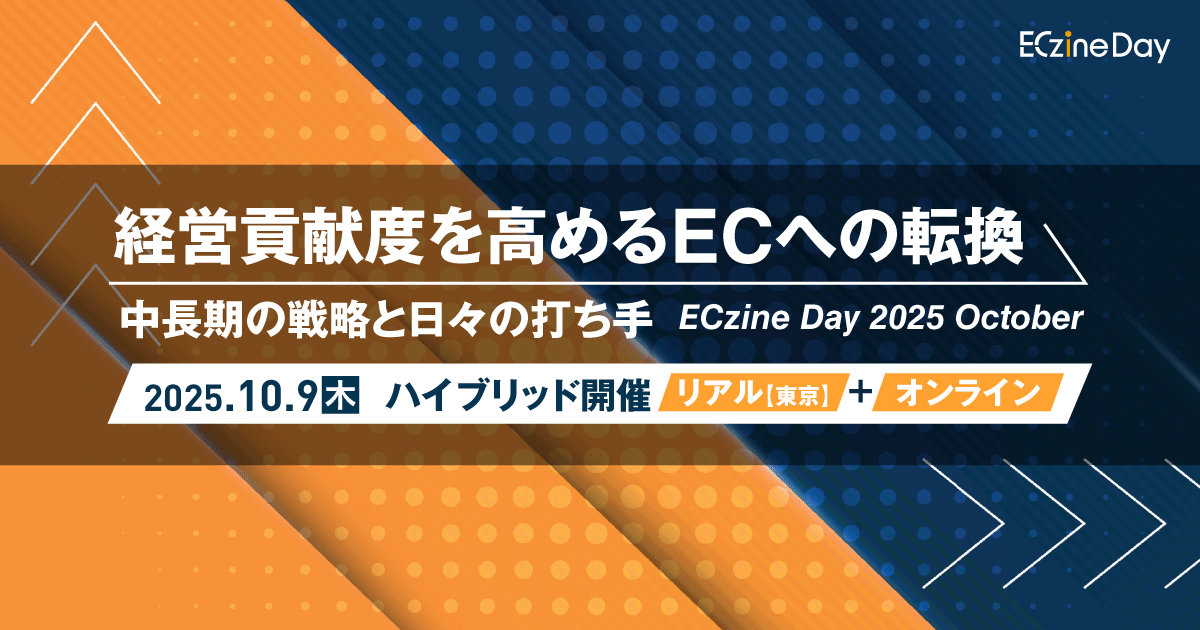ラストワンマイルとは
近年、物流業界を中心によく耳にする「ラストランマイル」。さまざまな分野でも使われるようになり、どのような意味なのかを理解したいという人も多いことでしょう。
そこで、本章では各分野における「ラストワンマイル」の意味を解説します。
通信における「ラストワンマイル」
「ラストワンマイル」とはもともと通信業界で使われていた言葉であり、「最後の1マイル(※マイルは距離の単位)」という意味です。通信業界においては、最寄りの基地局から利用者の建物や端末までをつなぐ、通信回線の最後の区間のことを指しています。
交通における「ラストワンマイル」
交通分野での「ラストワンマイル」は、目的地までの最後の区間を指します。たとえば、最寄り駅やバス停から自宅へ向かうまでの区間をラストワンマイルと言います。
地方は過疎化・高齢化が進み、経営難で公共交通機関の運営を維持できない地域や、自動車免許を返納したことで運転できなくなった人が少なくありません。そうした地域や住民が交通手段を確保できるよう、乗り合いタクシーのような「ラストワンマイル・モビリティ」が求められています。
物流における「ラストワンマイル」

物流において「ラストワンマイル」とは、最寄りの配達事業所から届け先までのことを指します。これは物流業界において、顧客との最終的な接点でもあります。たとえば、大手のEC事業者は顧客に近い場所に配送拠点を作り、ラストワンマイルを縮めることで、全国配送や翌日配送などのサービスを実現しています。
ネットショップの増加やライフスタイルの多様化で、消費者が購入した商品を好きな時に受け取ることは、もはや常識と言えるでしょう。そのため、人の手を介する「ラストワンマイル」ではさまざまな課題が生まれ、早急な解決が求められています。
営業における「ラストワンマイル」

営業におけるラストワンマイルとは、「顧客が商品やサービスを購入するに至った決め手」のことを指します。通信業界や物流業界における定義と同様、顧客に商品やサービスを届ける上で、購入・契約に至るところが最後の接点になるためです。
これまで、BtoB・BtoCのいずれの商談においても、顧客が商品やサービスを購入するに至った決め手は本人にしかわからないことでした。しかし、近年ではデジタルテクノロジーの発展やインサイドセールスの需要増加により、Web解析などを行って「ラストワンマイル」をデータ化することも徐々にできるようになってきたのです。
物流におけるラストワンマイル問題と課題
物流におけるラストワンマイルには、さまざまな問題点が指摘され、特に以下の4つは早急に解決すべき課題点となっています。
電子商取引増加にともなう宅配需要の増加
ECサイトやECモールの台頭により、インターネットを介して遠隔地で商取引を行う「電子商取引」が主流になっています。
経済産業省によると、2023年の国内におけるBtoC電子商取引の市場規模は24.8兆円となっており、前年の22.7兆円よりも約2兆円の成長です。また、BtoBにおいては465.2兆円で、前年は420.2兆円だったため40兆円以上成長していることになります。
これにともない、宅配便も多く流通するようになっています。宅配の需要が増えると、それだけ人手やトラックなどを用意しなければならず、今までと同じリソースでの経営は厳しくなっているのです。
高齢化などによる労働力(配達ドライバー)不足

増え続ける配達物に対し、配達ドライバー不足が最もよく指摘される課題です。宅配便の取り扱いは年々増え続け、2020年からはコロナ禍の影響もあいまって通販の需要はさらに増えています。
しかし、そもそも少子高齢化の影響で労働力不足の日本では、ドライバーのみならずどの職種も人手不足の状況です。さらに、配送料などのコストカットや、荷待ちや再配達などによる長時間労働など、ドライバーの待遇は悪い傾向にあります。こうした状況はドライバーのなり手の減少や、増えた宅配物の処理といった負担増のためさらに待遇が悪化する、という悪循環につながっているのです。
再配達によるコストの増加

再配達への対応は、ドライバー不足の問題とも密接に関わっている、物流のラストワンマイルにおける大きな課題の一つです。宅配物の数が増えるほど、不在による再配達率も高くなります。特に、宅配便の再配達を無料サービスとしている運送会社は多いため、ドライバーの長時間労働の一因となっています。
再配達や不在時の対応を無料で行うことにより、ドライバーの労力や人件費としてその負担はドライバー本人や運送会社にかかってきます。ラストワンマイルの不在時の配達や再配達を減らすことは、ネット通販が増え続ける現代において、最優先で取り組むべき課題とも言えるでしょう。
環境への影響
物流業界では、環境への影響も懸念されています。店舗への配送の場合は1度に多くの荷物届けますが、個人宅への配達の場合は配達件数に比例して荷物の数も増えるため、必然的に走行距離も長くなります。また、時間指定の荷物の場合には、時間内に届けるために過度な負荷をかけた運転になりがちです。
その結果、ガソリンを多く消費することになり、CO2排出量が増加して環境へ悪影響を与えかねません。
ラストワンマイル問題解決への取り組み
では、前述のようなラストワンマイルの課題を解決するために、物流業界ではどのような取り組みが行われているのでしょうか。今回は、5つの解決策をお伝えします。
輸配送管理システムの活用

輸配送管理システムとは、配送管理の段階で効率の良い配車や運行を行うシステムのことで、要員配置や積載率、荷物状況を把握した上で最適化し、人件費の無駄を大幅に省こうとするものです。
トラックの配車、移動データ、運賃、燃料代などをオンライン上で管理し、自動計算によって最も効率良い配車やルートを算出します。輸配送管理システムにはクラウド型、パッケージ型などさまざまな製品が提供されており、それぞれの運送会社が自社に合ったサービスを選ぶことが可能です。
輸配送管理システムを活用することで、自社に最適化した輸配送プロセスを設計でき、効率的な物流が実現するでしょう。
物流効率化のための最新テクノロジーの利用

AIや自動運転、配送ロボ、ドローンなどの最新テクノロジーを活用してラストワンマイルの人件費・人手不足を解消する方法です。これらは特にラストワンマイルに対する中長期的な取り組みとして研究・開発がなされているもので、さまざまな国や地域でさかんに実証実験が行われています。
日本ではヤマト運輸とDeNAが共同で実施した「ロボネコヤマト」の実用実験が有名です。現在は人間のドライバーが運転するトラックで保管ボックスまで荷物を運びますが、AIが搭載されており、ルート学習や安全運転のノウハウを積み込んで将来的にはAIによる自動運転を想定しています。
共同配送ネットワークの構築

現在、ラストワンマイルでは運送会社それぞれが個別に配達している状況です。しかし、さらなる合理化・効率化の観点からは、単一企業による一括納品拠点の構築が望ましいと考えられます。そのためには、各運送会社が密に連携し、共同配送の実現が必要不可欠です。
共同化・集約化で効率がアップすれば、無駄な輸送や作業などを排除でき、物流という流れ全体の改善が見込めるでしょう。また、前述のテクノロジーを適用するにあたっても、できるだけ同じエリアは同じ運送会社が担当すれば導入がスムーズです。物流全体の大きな改革にはなりますが、実現すれば大幅な業務改善につながるでしょう。
置き配など受け取り方法の多様化
再配達がドライバーにとって大きな負担となるため、置き配をはじめとする多様な受け取り方法を取り入れて再配達の件数を削減する必要があります。
自宅の玄関先や宅配ボックスへの置き配や、駅やスーパーなどに設置されている宅配ロッカー、コンビニや宅配業者営業所での受け取りなどが挙げられます。
サステナブルな配送手段
持続可能な社会を目指すには、配送におけるCO2排出量を減らして環境に配慮しなければなりません。そこで、サステナブルな配送手段が注目を集めています。たとえば、電気自動車、電動アシスト自転車、新幹線輸送などによる配送です。
日本通運株式会社は、株式会社ジェイアール東日本物流が提供する新幹線荷物輸送サービスを活用した配送の仕組みづくりを行っています。
ラストワンマイルの課題と解決策のまとめ
ラストワンマイルはもともと通信業界で使われていた言葉ですが、近年では物流業界や営業分野でもよく使われています。
特に物流業界におけるラストワンマイルの課題は深刻で、早急な解決が求められているのが現状です。デジタル技術を活用したり、サステナブルな方法を取り入れたりするなど、今後さまざまな工夫がされていくことでしょう。物流業界に携わる人だけでなく、宅配サービスを利用する人は「ラストワンマイル」を自分ごととして捉え、自分にできることを探してみてください。