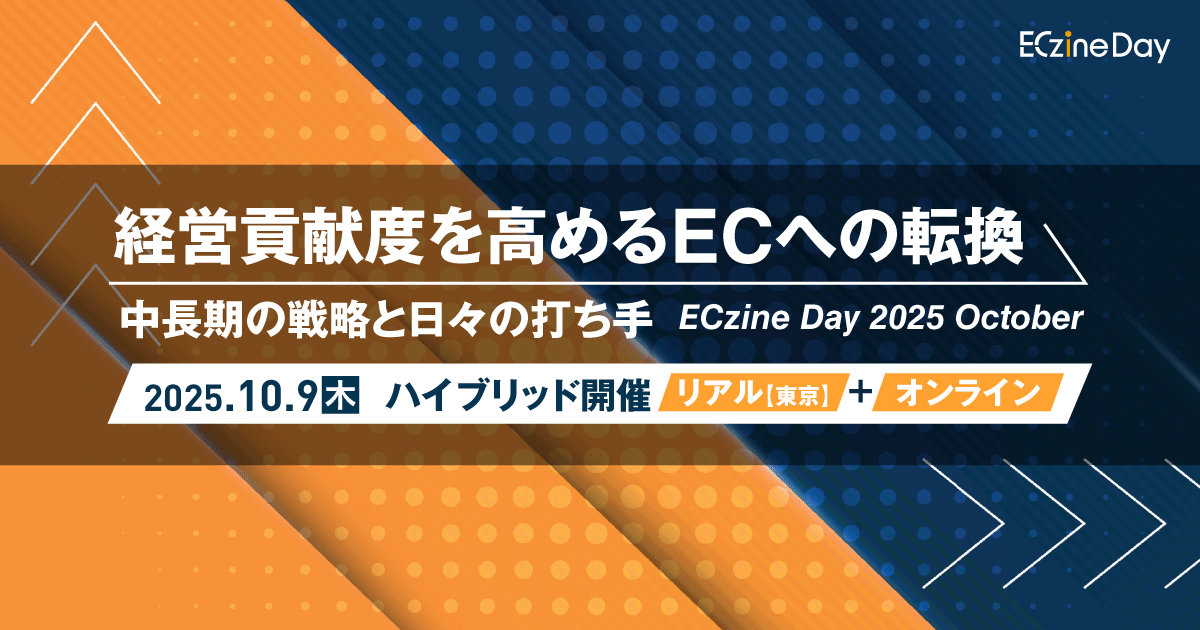世代横断で進行する“新しい消費”の形
近年、「○○消費」と様々な場面で耳にするようになった。それだけ消費者の購買行動が多様化しているといえるだろう。その一つとして徐々に浸透してきたのが「リキッド消費」だ。

リキッド消費は、モノを所有せず経験を重視する、商品やサービスを選ぶのに時間をかけないといった特徴がある。わかりやすい例が『リキッド消費とは何か』(新潮新書/久保田進彦 著)でこう紹介されている。著者が大学で講義をした際の学生のレポートだ。
祖母は私に「いいものを長く使う」のが大切だと教えてきました。確かに祖母はデパートで買ったものを長く使っています。しかし私はどちらかと言うと「コスパがいい」ものを何回も買うことによって、気分を変えたり、より多くの購買の機会を楽しんでいます。(Aさん)(P.65-66)
このような消費の考え方を「若者ならでは」「Z世代の特徴」と捉える人もいるのではないだろうか。しかし、実際にはより複雑だ。著者による調査・分析では、リキッド消費の傾向が若年層で顕著な一方で、40代~70代でも同様の傾向が強い層が存在するという。とはいえ、単に彼らがまったく同じような消費行動をとるわけではない。リキッド消費の中にもグラデーションが存在すると理解する必要があるだろう。
モノを所有するのは古い? 消費行動の変化を正しく追う
リキッド消費の対義語に「ソリッド消費」がある。モノの所有に重きを置く、いわば従来型の消費行動だ。この考え方が徐々に薄くなってきているとはいえ、完全なるリキッド消費に世の中がよっていくと断言はできない。むしろ久保田氏は、本書内で「リキッド消費の出現で世界が一変したと考えるのは早合点(P.64)」としている。
これまでの消費生活が「古くなった」のではなくて、私たちが「もう1つの消費スタイルを獲得した」と考えるのが適切です。(P.64)
本書では、こうした実際のリキッド消費の行動について多くの調査データを活用して解剖する。たとえば、「実店舗では1ヵ所で買い物を終わらしたいが、ECサイトではあまり気にしない」「PB(プライベートブランド)を好んで買う傾向がある」といった特徴は興味深い。マーケティング施策、自社ECサイトの改善案の参考に読んでみてはいかがだろうか。