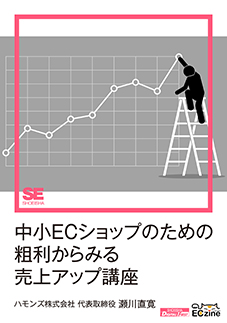LINEが考えるDXの定義 鍵を握るのは「ユニバーサルエクスペリエンス」
次にLINEの比企氏から、日本マイクロソフトとLINEの取り組みについて説明がなされた。同氏は「これからのDX」を考える上で重要なふたつの軸についてこう語る。
「『不特定多数の人と向き合うのか』、『個人と向き合うか』。このふたつの軸が重要となります。前者で考えるべきは『店舗を訪れた顧客の行動の可視化』、後者で考えるべきは『顧客との1to1の応対をアプリを活用してどのように実現するか』です」(比企氏)
LINEは、2022年3月時点で国内月間ユーザー数(MAU)が9,200万人、事業者・店舗によるLINE公式アカウント数は37万(※2022年3月時点のアクティブアカウント:認証済みアカウントのうち、月に1度以上機能を利用しているアカウント数)を超えている。比企氏は、「LINE API」の活用により広がる可能性について、こう続ける。
「LINE APIは、LINEのインターフェイスと事業者のバックエンドシステムを連携できる仕組みです。同APIを用いることで、LINEを使った顧客の活動を自社のデータベースに保存したり、自社のデータベースに蓄積された情報を基にLINE公式アカウントにプッシュ通知を送ったりといったアプローチが可能です。こうした施策展開ができる土壌を活かし、日本マイクロソフトとLINEで流通・小売業における新たな顧客体験を提供していきます」(比企氏)

続いて比企氏は、LINEが考えるDXの定義について話を進める。
「当社は『DX=CX(顧客体験)+EX(従業員体験)』であると考えています。CXを突き詰めると『UX(ユーザーエクスペリエンス)』にたどり着きますが、企画者は『ユニークエクスペリエンス』に陥りがちです。たとえば、会員証や切符などの権利を表すものは、本来の利便性を考えると統一したデザインであるべきですが、開発者やデザイナーはついデザイン性を重視してしまうがために、顧客が望むものや運用の視点から外れたものになるケースも多々存在します。
こうした事態を避けるために、LINEではUXを『ユニバーサルエクスペリエンス』ととらえています。顧客視点で考えれば、事業者やサービスの垣根を越えて同一のインターフェイスを活用できたほうが利便性は向上します」(比企氏)
たしかに、LINEを活用して行う施策はインターフェイスが統一され、デジタルにそこまで明るくない利用者でも比較的容易に操作・サービス利用が可能となる。すると課題になるのは差別化であるが、LINE APIを用いてパーソナライズした情報提供や新たな体験創出ができれば、こうした懸念も解決できるだろう。
なお、LINEは事例を集めたウェブサイト「LINE API Use Case」を開設。同サイトには、LINEを活用して会員証を提示したり、スマートフォンレジによる購買手続きを実現したりと、OMOのさまざまな事例がデモ形式で紹介されている。「TECHNICAL CASE」のコーナーでは、LINE API活用事例に用いられている技術のシステム構成図やシーケンス図を見ることも可能だ。

「DXは、文章のみで議論すると空中分解しやすいため注意が必要です。デモやLINEを使い、目で見て触って体験することでイメージしやすい状況を作り上げています」(比企氏)
ここで比企氏は、「DX=CX(LINE)+EX(従業員体験)」であると提示。「CXはLINEで生み出すことができる」と語った上で、「『+』の部分を日本マイクロソフトとLINEのクラウドで提供する」と語り、日本マイクロソフトの井上氏にバトンをつないだ。