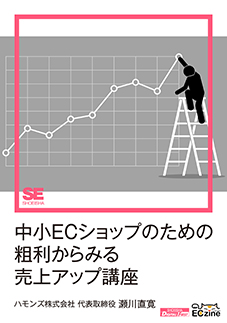D2Cの本質は商品とともに情報を届けること 口コミ・レビュー活用が鍵に

自社の商品を直接消費者に販売・提供するビジネスモデル、D2C。従来のメーカー直販などとの大きな違いは、商品の背景にある企業の想いや価値観などの「情報」も合わせて消費者に届ける点にあると山崎氏は説明する。
「D2Cにおいては商品の販売だけでなく、商品を購入する消費者とのコミュニケーションがとくに重要な意味を持ちます」(山崎氏)
続いて山崎氏は、消費者の声として「メーカー・ブランド直販サイトでの不満」についてのアンケート結果を紹介した。
アンケート結果によると、「送料が高い」「サイズ感がわからない」「手触り・香り・色味などがわからない」などが不満の上位に挙がっている。これらは店舗で購入する場合には発生しない、オンライン特有のデメリットだ。
「つまり、店舗では当たり前に提供できていた顧客体験(CX)の一部が従来型の直販サイトには欠けており、消費者が求める必要条件を満たしていないということです。まずはいかにその穴を埋め、改善できるかを考えなければなりません」(山崎氏)
商品の実物を見て、触れることができる店舗とまったく同じCXを提供することは物理上困難ではあるが、「オンラインならではのデジタルテクノロジーを活用した代替手段で、欠けている部分を補うことはできる」と山崎氏は言う。その手段の具体例として挙げたのが、口コミ・レビュー・Q&Aの活用だ。
たとえば洋服のサイズ感を知りたい場合には、自分と体型が近い人による「Lサイズでは大きかった」などの口コミ投稿が参考になるだろう。また、消費者の質問に企業の担当者やサイト運営者が回答する「商品Q&A」といった場を設けることにより、正確な商品情報を提供できるほか、店舗におけるスタッフとのコミュニケーションの代替にもなる。そのほかには、Amazonが提供する「カスタマー Q&A」のように、消費者の質問に対して別の消費者が回答するという、消費者同士でのコミュニケーションが行われるケースも存在する。
「実際にその商品を購入して使っている人や、販売元の担当者による意見・回答から情報を得ることは、『店舗で商品の実物を見る』というCXの補完として、非常に有効な手段です」(山崎氏)
さらに山崎氏は、「レビューを活用すれば店舗で得ることが難しい情報も入手できる」と続ける。店舗で接客するスタッフは商品情報に詳しく、質問に対して的確な回答を返してくれるが、自社商品・サービスに対してネガティブな発信はしないだろう。消費者に商品の魅力を伝え、購入してもらうのが職務なため、「隠す」という意識はなくてもマイナス面に対する評価が甘くなる可能性もある。これに対して、消費者によるレビューには「自分には合わなかった」「期待したほどではなかった」といった評価も混在している。
「商品とともに情報も消費者に届けるのがD2Cの本質です。ネガティブな情報も隠さず、あらゆる情報に消費者が容易にアクセスできるようにすること、スムーズに情報収集できるようにサポートすることが求められます」(山崎氏)
つまり、ポジティブな情報とネガティブな情報、どちらも知った上で消費者が総合的に判断し、納得して購入してもらうことが重要ということだ。

山崎氏は、レビューが10件になるとCVRが1.5倍、50件では2倍になるという海外の事例を紹介。「たとえばAmazonや楽天市場で、レビューが1件もついていない商品を購入するのは、ためらう人も多いのではないだろうか」と問いかけた。
ECの検索機能は接客そのもの 消費者の期待を裏切らない改善を
もうひとつ、店舗でのCXにおいて重要となるのがスタッフの存在だ。求めている情報を直接提供してくれるスタッフとの会話も、消費者が店舗へ足を運ぶ大きなモチベーションとなる。
「スタッフが存在しないECで、代替手段となり得るのがサイト内検索の機能です。ECにおける検索は、『消費者と販売元との対話』だととらえてください。検索に入れる条件は、『店舗でスタッフに投げかける質問』と考えると良いでしょう」(山崎氏)
たとえば、「探している商品の種類」「サイズや色」「予算」などをスタッフに伝える代わりにEC上で絞り込み検索を使い、「新商品」「人気の商品」「お得な商品」などを聞く代わりに、検索結果の並べ替えを用いるというわけだ。
優れた検索機能を実装していれば、店舗で優秀なスタッフが質問に対して的確な答えを提示するように、適切な検索結果を提供することが可能だ。一方、検索機能がきちんと機能していない場合、店舗で在庫の有無を正確に回答できない、商品に対して誤った情報を提供してしまうスタッフを配置していることと同じと言える。そのため、不満を感じた消費者は「気持ち良い体験ができない店」と認識した上で離脱、二度と来訪しない可能性もある。
「検索を行う消費者は積極的にものを買おうとしている可能性が高く、『良い商品を探したい』『見つけたら教えてほしい』という状態です。そこに対して的外れな検索結果を出してしまうのは大きな機会損失であり、消費者の期待を裏切ることになりかねません。もし既存の検索機能が弱いと課題を感じている場合は、ぜひ改善しましょう」(山崎氏)
途切れることなく消費者とつながる エンドレスアイルを体現する「ZETA CLICK」
コロナ禍が収束し、店舗への人の流れが回復した際により重要となるのが、OMOの取り組み、とくに「店舗でのデジタル活用」だと山崎氏は主張する。もちろん店舗においてもオフライン固有のデメリットは存在するが、それらの多くは店舗でのデジタル活用を推進・拡張することで解消できると言う。
「かつては『店舗=アナログ』『EC=デジタル』として、対立概念のように扱われてきましたが、実際はそうではありません。店舗は『場所』であり、ECは『情報流通の手段』。つまり、そもそも軸が異なる概念です。
店舗でより良いCXを実現するには、デジタルを活用しやすい環境を整える必要があり、それはD2Cの店舗展開にもつながります。D2Cも現状はECで展開するイメージが強いですが、本質的には消費者に商品だけでなく、さまざまな価値や情報を届けるための取り組みであり、提供する場所は関係ありません。むしろ、あらゆる場所で消費者とつながることを目指すもので、OMOと密接に関連した概念と言えます」(山崎氏)

また、最近ではOMOの発展型となる概念「エンドレスアイル」も注目されていると山崎氏は続ける。
「アイルは、通路という意味を持ちます。本質的にはOMOと近しい考えですが、オンライン・オフラインを問わず、途切れることなく消費者とつながり、継続的にCXを提供することを目指すものです」(山崎氏)
ここで山崎氏は、エンドレスアイルを体現するOMO・DXソリューション「ZETA CLICK」の利用イメージ動画を紹介した。同ソリューションでは、店舗でスタッフがコーディネート提案をした際に、同時に商品のバーコードをスキャンすることで、その消費者専用の商品情報ページを作成できる。

スタッフは自動発行された二次元コードを消費者に見せ、専用ページを共有。同ページは店舗の外からも閲覧できるため、消費者は帰宅中や自宅でじっくり商品検討が可能だ。店舗からは購入を促すアプローチとして、メッセージやクーポンを送付、購入を決断した消費者は店舗に再来訪した際に用件を伝えることなく、スムーズに希望する商品を手に入れることができる。
なお、購入時の決済もレジを介さずスマートフォンで完結、配送を希望する場合はスマートフォン経由で手続きすれば商品を持たずに帰宅することも可能だ。店舗側は、こうした消費者とのやり取りや顧客情報をパソコンやタブレットなどのデジタル端末で管理し、スタッフの接客情報を把握、評価の適正化やモチベーションの維持などにもつなげることができる。
「店舗を含めたデジタル活用のソリューションにより、消費者が店舗を出た後も継続的にコミュニケーションを取ることが可能となります。不快感を与えない頻度、かつ同意を得た上で行えば、これは非常に有効なアプローチとなり得ます。『ZETA CLICK』はCRMの面でも効果的で、初回に接客したスタッフが不在の場合も、別のスタッフが接客履歴情報を共有してシームレスに対応できます。これは、店舗のCX向上につながることでもあります」(山崎氏)
最後に山崎氏は、D2Cを進める上でのポイントを次のように語り、セッションを締めくくった。
「D2Cへの取り組みで重要なのは、消費者と真摯に向き合い、常にCX向上を意識することです。D2Cはオンラインに限られたものではなく、オフラインと併せて推進することも求められます。検索機能やレビューの活用は、現段階でOMO推進する上で有効なツールとして作用します。ぜひ積極的な活用をお薦めします」(山崎氏)