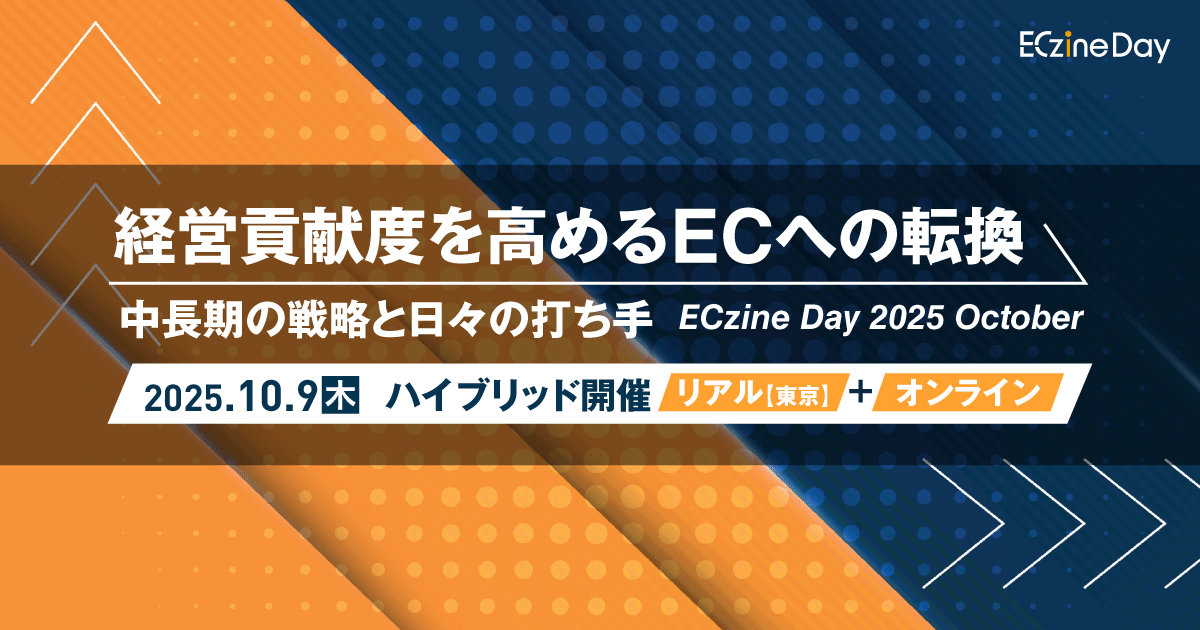企業価値を変革するカスタマーエクスペリエンス(CX)の本質
BtoCパートの特別講演には、Mizkan Holdings 渡邉英右氏が登壇した。Chief Digital Officerとして、全社のデジタル化を推進、顧客中心の考えかたを全社に広めるのもデジタル戦略本部だと言う。

ミツカンの企業理念には「2つの原点」がある。ひとつは「買う身になって まごごろこめて よい品を」であり、顧客体験を重視した姿勢であると渡邊氏。もうひとつは「脚下照顧に基づく現状否認の実行」であり、古くからイノベーションを重んじる企業姿勢を示している。そしてもうひとつ、グループビジョン・スローガンには「やがて、いのちに変わるもの。」を掲げており、食品を製造する企業として、顧客に提供していく価値を示したものだと言う。
こうしたミッションを踏まえ、デジタル時代の、とくに製造業の顧客体験(CX)はどうあるべきか。渡邊氏は、次の3つの考えかたを提示する。
- 習うより慣れよ
- 顧客中心のカルチャー
- 顧客中心活動を支える仕組みとしてのプラットフォーム
まず、「習うより慣れよ」については、製造業は企画開発の段階で非常に考え込むが、デジタルの時代は作ったものを変更するのは難しくない。ひとの考えかたを、とりあえずやってみるというものに変えていくという。ミツカンの取り組みとしては、「未来ビジョン宣言」のサイトをリニューアル。A/Bテストを行うなどして、「とりあえずやってみる」の文化を浸透させていった。
次の「顧客中心のカルチャー」は、まさにCXに関することだ。従来、製造業と生活者のコミュニケーションは、マスコミュニケーションが中心だった。それがデジタルの時代になり、1人ひとりの生活者を向き合うことができるようになり、コミュニケーションの仕方もそう変えるべきなのである。ミツカンでは、デジタル戦略本部のメンバーが実際に街中に出かけて生活者を観察したり、デザインシンキングを取り入れ、さまざまな意見が出るようなカルチャーづくりに取り組んでいると言う。
そして、「顧客中心活動を支える仕組みとしてのプラットフォーム」だが、「顧客プラットフォーム」にしろ、「エンタープライズプラットフォーム」にしろ、個別最適だったり、ブラックボックス化しているという課題がある。それを生活者起点で、ミツカンの未来ビジョン宣言の考えかたを継続的に伝えるべく、自分の部署、自分の国だけでなく、全体最適のプラットフォームに変え、業務を標準化していくべきだと考え、設計・構築を進めていると言う。
最後に、企業として全社的に取り組むには、サポーターを増やすことも必要だと述べた。
BtoC企業のデジタルトランスフォーメーションを考える
パネルディスカッションは、アビームコンサルティング 本間充氏のモデレートで、デジタルトランスフォーメーション(DX)をメインテーマに行われた。ミツカン 渡邉氏、カッシアーノ氏のほか、パネリストとしてワークマンを同グループ企業に持つベイシア 竹永靖氏が登壇した。
まず、各社のDXの現状や取り組みはどうなっているのだろうか(本間氏)。
「入社してまだ10ヵ月ほどですが、はじめの半年はミツカンのこと、製品のことを理解し、仲間に入れてもらうことを優先し、DXについてはほとんど何も言わずにいました。当社の特徴として、オーナー企業であり、ミッションにデジタル化が明確に入っていることです。上からのサポートがあり、DXの推進に努めて報われないということはありません」(渡邉氏)
「ことCXに関することで言うと、小売の場合、一度は来てくださるお客様は多いのですが、リピートしていただかなければビジネスとして成り立ちません。いかに、2回目、3回目に来ていただくかを追求しています。取り組みの一例として、たとえば『工具とビール』のような意外な合わせ買いと、そういったお買い物をされるお客様をデータ分析で導き出しています。それをもとに、メーカーさんとコラボして商品を作ったり、メーカーさんとマーケティングデータを一部シェアするということもやっています」(竹永氏)
「GAFAやウォルマートなどの先駆者たちは、CXが完璧でなくとも、需要と供給をつなぐことがスムーズにできています。ネットサーフィンをしていて、これを買おうとサイトを開いたら、その商品の入荷は3日後になる、とあったらそこでドロップアウトしますよね。需要と供給をスムーズにつなぐことは、それほど重要なのです」(カッシアーノ氏)

いち企業を越えたDXとして、流通小売とメーカーが一緒に作るエコシステムは果たして実現可能なのだろうか(本間氏)。
「データによって顧客理解をするだけでは足りず、それを活かしてどうコミュニケーションをするかが重要ですよね。以前からある考えかたですが、ファンベースやアンバサダーがここに来てハイライトされています。もともとミツカンに対して満足度が高く、ロイヤリティが高い生活者にご満足いただき、リーチできていない新規顧客にいかにタッチできるかがキモになると思います」(渡邉氏)
「SAPが一緒に取り組んでいる企業は、ブランドのロイヤリティを高めようと、ゲーミフィケーションを取り入れています」(カッシアーノ氏)
「日本の成功例としては、トライアルカンパニーではないでしょうか。お店に行ってみると、高齢者の方もあのカートを押して、ポイントを貯めていらっしゃるんですよね。そのデータをメーカーに提供するのはもちろん、システム自体を小売業にも販売しようとしているのだととらえています」(竹永氏)
最後に本間氏は、BtoCの場合生活者のDXが早いため、渡邊氏が講演で述べた「生活者の観察」は重要ではないかと指摘。そして、本イベントのテーマであるXデータとOデータの組み合わせで新しいビジネスを作っていくことが重要であり、DXに終わりはないとまとめ、パネルディスカッションを締めくくった。
イノベーション&製造業のDXがわかる!資料ダウンロード
本イベント「SAP CX DAY 2019」にて、SAP ユージニオ・カッシアーノ氏、コニカミノルタ 仲川幾夫氏が講演した際の投影資料(抜粋版)をダウンロードいただけます。詳細・ダウンロードはこちら。