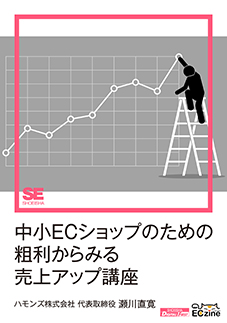どんな立場の人でもデータ活用しアクションできる 「KARTE」のOMO推進

CXプラットフォーム「KARTE」を提供するプレイドは、オンライン上でも店舗同様に「人対人」の温かいコミュニケーションが行われることを目指してサービス提供を開始。機能開発・拡張を進め、現在ではオンライン・オフライン双方の顧客データ活用ができるサービスとなっている。
同社が掲げるミッションは、「データによって人の価値を最大化する」である。企業内のどんな立場の人でも顧客データを利活用できるようにし、顧客1人ひとりの行動に対する解像度を上げることで顧客と目線を合わせたアプローチを実現。顧客満足度向上のみならず、企業の新たな価値創造を目指している。こうした思想を反映した「KARTE」は、「OMO推進にも強みを発揮する」と阪氏は語る。
ウェブやアプリ上といったオンラインのみならず、店舗などオフラインのコミュニケーションで収集したデータも人軸で統合。人の動きを可視化した上で多様なアクションにつなげ、LTV向上に寄与する「KARTE」について、阪氏は「OMO施策に活きる3つのデータ特性を持っている」と説明する。具体的には次のとおりだ。
1. リアルタイムに人軸でデータを溜める
たとえば、オンライン上で検索して気になる商品を見つけ、店舗で実物を確認して購入する。もしくは、店舗で試着したがその場では購入せず、検討の後にオンラインで購入する。こうした行動は消費者にとって当たり前となりつつあるが、企業側が顧客1人ひとりの実態を把握できていないケースはまだ多い。チャネルをまたいだ行動の可視化ができていないかぎりは、「なぜ」といった理由の部分まで深掘りすることも難しい。
こうした企業の状況を踏まえ、顧客がどこで商品を知り、いつ購入したいと思い、実際にどのような行動を取ったのかをリアルタイムで解析し、時系列に沿って人軸でのデータ保持を実現したのが「KARTE」だ。オンライン・オフラインとチャネルをまたいだ行動についても人軸で蓄積できれば、顧客1人ひとりの「今」とその行動にいたるまでの「理由」を解像度高く読み解くことが可能となる。
2. データを人として可視化する
「KARTE」で蓄積したデータは、社内の各部門がそれぞれ求める形で切り出すことができる。

OMOを実現する際に多くの企業が直面する「データ活用」の問題。部門やスタッフそれぞれの役割によって見るべきポイント、求めている情報が異なることを踏まえ、「KARTE」ではデータをさまざまな形で可視化し、顧客を直感的に理解できる環境を整えている。自らが求めるデータを容易に収集できるようになれば、実態に基づいた気づきから「こんなアプローチをしたら喜んでもらえるのでは」と、スタッフ1人ひとりが自主的にアクションを起こしやすくなる。同じデータに基づいて実践していれば、各部門の施策がぶれることなく、一貫した顧客体験を提供することも夢ではない。
3. ワンストップで多様なアクションにつなげる
「プラガブル(接続可能)」という思想で設計されている「KARTE」は、リアルタイムで解析したデータを多様なアクションやデバイスにつなげることができる。そのため、複数チャネルで横断的にデータを活用するデータプラットフォームとしても力を発揮する点に大きな特徴があると言える。
たとえば、Salesforce Sales Cloudに蓄積した顧客データをオンライン上の行動データと統合し、属性と直近の興味関心両方を掛け合わせたコミュニケーションの提供なども、「KARTE」では実現できる。このほかにも、Google AnalyticsやGoogle BigQuery、Snowflakeなどさまざまなデータとの連携が可能だ。

単発もしくは限られたチャネルの体験から得たデータのみに目を向けているようでは、今の時代の顧客に即したOMO推進は難しい。オンライン、オフライン問わず、各チャネルで得た顧客のアクションを次の接点で活かすこと、つまり人軸でデータ蓄積・活用を行い、文脈がつながった体験提供が必要となる。では、「KARTE」を活用することで具体的にどのような示唆を得て、連続性のある顧客体験作りができるのだろうか。
ECは情報収集の場、お気に入り登録はメモ代わり クロスユースする顧客の実態
ここでスピーカーが阪氏から宮下氏に変わり、文脈がつながった体験提供を実現するための「知る」重要性について紹介がされた。

OMOを実現するには、「取得した顧客データをN=1の解像度で見る必要がある」と宮下氏は強調。「オンライン・オフラインで横断的な価値を表現するには、人軸でデータを蓄積することが不可欠。そうすることで、初めて顧客を理解できる」と続ける。
ここで宮下氏は、あるアプリを使う顧客へのアンケートをもとに、オンライン・オフラインのデータを統合することの意義を解説した。オンライン上で行った同アンケートで「店舗に行くきっかけ(理由)」と「店舗に行く際、もしくは店内で知りたい情報」について聞いたところ、前者は「ウェブサイトで見た商品の実物を見るため」がトップとなった。なお、後者は「(ウェブ上で)お気に入り登録したアイテムの情報」という結果になっていると言う。
あくまでひとつのアンケートから導き出された結果だが、オンライン・オフライン双方のチャネルを有する企業で購入検討する顧客は、ウェブ(EC)を店舗に足を運ぶ前の情報収集手段として活用し、メモ代わりにお気に入り登録している様子がうかがえる。
さらに別のブランドでは、会員登録をしているユーザーを対象にEC・アプリの利用データと店舗のPOSデータを定量的に分析したところ、「店舗で商品購入・会員登録した顧客の約70%が当月中にECに来訪」「EC購入者の約30%が当月中に店舗でも購入」していることが明らかとなっている。つまり、自社の会員になってくれているロイヤリティが高い顧客は各チャネルをクロスユースしており、EC・アプリの存在が店舗の売上にも寄与していることが見えてきたのだ。すると、これらのチャネルをどう使い分けるべきか、オンライン・オフラインそれぞれでどのような商品をアピールしていくかといった、より顧客の実態に合った施策検討が必要となる。
「N=1の解像度で見なければ、こうした示唆を得ることはできません」(宮下氏)
N=1の解像度でデータを見れば、スタッフの発想も豊かになる
「KARTE」では、クロスユースする顧客が増加する現代に合わせたN=1のデータ収集を実現できるが、こうしたデータをどう活用するかも重要となる。
「オンラインでもオフラインでも、データを活かしてスタッフの発想を豊かにしていく。それが良い顧客体験を生み、OMOを実現するための重要なポイントです」(神尾氏)

神尾氏は、ここから「KARTE」活用でOMOを実現する企業の実例を紹介した。アウトドア・アパレルメーカーのゴールドウィンでは、ECに来店する顧客と店舗スタッフをリアルタイムでつなぐ「KARTE GATHER」を用いて、国内13の店舗とECのOMOを実現している。
まるで実店舗にいるかのように会話が実現できる「KARTE GATHER」は、一見すると単なるビデオ接客ツールのようにも見られるが、「性質は異なる」と神尾氏は説明する。同プロダクトはECに来店した顧客の趣味嗜好を「KARTE」のデータを用いてリアルタイムで把握し、最適な店舗スタッフが接客を展開できるような仕組みとなっている。
たとえば、顧客が「富士山に登りたい」と考えている場合、ファッションに詳しい店舗スタッフが接客するとアンマッチになってしまう可能性もある。しかし「KARTE GATHER」を用いて顧客が登山用品を探している意図が理解できれば、登山好きな店舗スタッフが接客するといった「接客の最適化」が実現可能だ。わざわざ該当する店舗スタッフがいる場に足を運ばずとも、自宅にいながら求めている情報を得て、買い物を楽しむことができる。これが、同プロダクトの提供する新たな顧客体験である。

顧客体験をより豊かに 業種別「KARTE」活用のシナリオを解説
デジタルツールが発展し、さまざまな手段でOMO推進を図ることができる時代ではあるが、「ただつなぐだけでなく、顧客にとってどのような価値になるか感じ取ることが重要」と神尾氏は語る。顧客に対する解像度を上げ、より良い顧客体験の提供を実現すべく、プレイドでは「KARTE」と連携する3つのOMOソリューションを提供している。
1. 顧客の思惑を理解する「レポート」
「KARTE」に蓄積するデータを用いて、顧客の状態を知るためのカスタマーレポートを作成できる機能。旅行代理店を例に挙げると、来店以前に顧客がどのようなウェブサイトを見ていたのか、どのような時間帯にそれらを閲覧していたのかをレポート経由で理解した上で接客を実施するといったように、顧客の行動や意向に応じたコミュニケーションを実現できる。「グアムに行きたい」「ダイビングがしたい」というニーズがある顧客に対して、それらに詳しいスタッフをマッチングしたり、閲覧していた観光スポットに関連した情報を収集・提供したりすることで、顧客体験向上を図ることが可能だ。
2. 顧客から能動的な意思表示を受け取る「チェックイン」
同機能は、顧客が店舗来店時にスマートフォンアプリや二次元コードを活用してチェックインすることで、趣味嗜好や過去の購買記録に基づいた情報提供を実現するもの。店舗スタッフも店内の端末などを用いて情報を把握し、声がけのタイミングや適切な商品提案、顧客との円滑なコミュニケーションに役立てることが可能となる。

3. 自宅で店頭を実感できる「ビデオ接客」
同機能は、前出した「KARTE GATHER」を用いた店舗スタッフのマッチングを指す。店舗スタッフの専門性や顧客の趣味嗜好に合わせたアサインを企業側から行うことで、波長の合う接客や満足のいく体験提供を実現する仕組みとなっている。
続いて神尾氏は、これらのソリューションを活用した業種別のシナリオを紹介した。
アパレル
あらかじめEC上での行動などから顧客のコンプレックスや好みなどのデータを収集し、「KARTE」に蓄積。来店時にチェックインをしてもらい、蓄積されたデータに基づいた接客を店舗スタッフが提供する。万が一その場で購入に結びつかなかった場合も、来店情報や接客の履歴がすべて「KARTE」に残るため、顧客が自宅で再検討する際にも好みに応じた情報を表示することが可能となる。
コスメ
美容スタッフの知見や接客が重要となるコスメにおいては、店頭接客のみならずビデオ接客を用いた手厚い対応も欠かせない。いつでもどこでも「興味がある」「購入したい」という気持ちに寄り添い、意欲を高めることが鍵となる。
ショッピングモール
家族で買い物、カップルでデート、ひとりでウインドーショッピングとさまざまな客層・シチュエーションが存在するショッピングモールでは、顧客の情報を事前に把握することがたいへん重要となる。たとえば、子連れで来店することが多い顧客に対して子ども向けイベントを告知すれば、来店促進が可能だ。また、チェックイン機能を活用すれば来館者調査を素早く実施できるため、企画の高速アップデートも実現できる。
不動産
ウェブ・アプリ上で、たとえば「AとB、どちらに住みたいか」といったアンケートを実施。回答内容に応じた情報の出し分けを行うことでレコメンドの精度を上げ、展示場来訪時には顧客の気になるポイントに合わせた説明を行うことで、CVRにつなげることも可能となる。
ホームセンター
顧客がどのフロアに入ってきたかをデータで可視化することで、売場作りの最適化を実現。データを踏まえて陳列位置を決め、店舗スタッフのアイディアを活かした展開方法で効果を最大化。能力開発やモチベーション向上にも「KARTE」は寄与する。
こうした事例を踏まえ、神尾氏は最後に改めてN=1で顧客を理解することの重要性について語り、セッションを締めくくった。
「企業が今まで蓄積してきたデータは財産です。『KARTE』を導入し、N=1で顧客を知ることができれば、体験をより豊かにすることができます。すると、顧客の満足度が上がるだけでなく、スタッフにとっても顧客の解像度が上がり、モチベーションアップにつながります。当社は、皆様の体験が変わるお手伝いをしたいと考えています」(神尾氏)