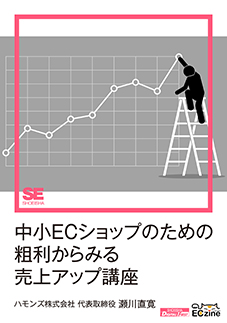CX(顧客体験)を重視すれば、OMOに行き着くのは必然
この10年ほどの間でマーケティングにおける最大の転換点ともいえるのが、スマートフォンの登場・普及だ。かつてのPC並みかそれ以上に処理性能が高く、常時ネットワークにつながったデバイスをほとんどの人が持ち歩くようになったことで、消費者の購買データや行動データを容易に取得できるようになった。
これにより、データを活用したデジタルマーケティングが飛躍的に進化し、カスタマージャーニーやUXといった新たなキーワードが続々と登場してきた。その中でも最も重要であり、総合的・俯瞰的な概念が「CX(顧客体験)」だと山崎氏はいう。
「OMO(Online Merges with Offline)も、このCXをベースに生まれた概念です。優れたCXをいかに創造するかを考えれば、OMOに行き着くのは必然ともいえます。優れたCXとは消費者にとって『ハッピーな買物ができた』と思える体験であり、オンラインで買うか、オフラインで買うかはまったく関係ありません」

店舗とECは対立概念ではない
OMO以前、さらにはO2Oやオムニチャネルといったキーワードが流行する前から、店舗(オフライン、リアル)とEC(オンライン、デジタル)は対立概念のように扱われてきた。しかし、店舗とECはそもそも「軸」が異なるものであり、対立する構図でとらえるのは間違っていると山崎氏は指摘する。
「あくまでもECというのは手段であり、店舗は場所です。『購入場所は店舗で、購入手段としてECを利用する』といったパターンも、ごく自然にありえることです」
まさにOMOの姿といえるが、これまでは店舗とECを対立する存在として考えてしまう誤解によって、そのようなことがなかなか実現できなかった。CXの概念が広く浸透したことで、ようやく両者は二律背反ではなく軸が異なり、連携・融合できるものであることが認知されてきたというわけだ。
今後さらにOMOが進展すると、店舗やECの役割はどのように変化するのか。山崎氏は、「決済以降はECへの集約が進み、店舗はマーケティングの一環として機能する」と説く。
「購買の本質的なプロセスは、決済と商品の受け渡しです。そこは消費者にとってもマーチャントにとってもオンラインでデジタル化したほうが利便性が高いので、大部分をECが担うことになるでしょう。一方、店舗は実際に商品を見たり、触れたりできるという圧倒的な強みを活かし、決済より前の商品選択のプロセスに特化した、『商品を体験する』というマーケティングのための場になるでしょう。これが、OMOの実現によって起こる重要な変化のひとつです」
店舗の役割とともに、物理的な姿も変化するという。たとえば、決済機能をECでカバーするようになれば、従来のような高額なレジ端末は不要となる。また、顧客がすぐに持ち帰りたい商品以外は、受け渡しもEC側の倉庫から発送すればよいので、大量の店頭在庫を持つ必要もない。それにより、在庫用のスペースだけでなく盗難対策として配置していた店員のリソースも最小限に抑えることができる。
続いて山崎氏は、こうしたOMOのメリットを活かした新しい店舗のありかたとして、「POP UP店舗」を紹介した。
OMOを体現する次世代の店舗のありかた「POP UP店舗」
POP UP店舗とは、期間限定でイベント的に出店する店舗のこと。日本ではまだそれほど見かけないが、山崎氏によれば海外ではかなり増えてきているという。
POP UP店舗は売場面積が限られていることが多く、大量の商品は持ち込めないものの、出店期間内に在庫切れとなれば大きな機会損失になってしまうという難しさがある。そこで有効なのが、店舗は体験の場として位置付け、決済以降の機能はECに任せるOMO型の販売スタイルだ。
事例として、ECで家具を販売しているベンチャー企業のPOP UP店舗を紹介。7月に香港で開催されたテックイベント「RISE」にその企業が登壇し、山崎氏はセッションを聴講して知ったそうだ。そのPOP UP店舗はショールームのように商品を体験できる場になっており、実際の商品購入はすべてEC経由で行う仕組みだったという。
「家具は配送扱いになるものがほとんどなのでECとの相性が良い一方で、実物を見てから購入したいというニーズも高い。まさにPOP UP店舗に適した商品といえます」(山崎氏)
実際に、そのPOP UP店舗では購入単価が30%向上、CVRも35%向上し、顧客への接触から購買までの時間は40%短縮されるなど、高い成果をあげたそうだ。

「日本でも限られたスペースでの商品デモンストレーションなどは見かけますが、それをECと連動すれば、POP UP店舗としてそのまま商品の販売まで行えるようになります。将来的には、主要駅構内などにたくさんのPOP UP店舗が並ぶようになるのではないでしょうか」(山崎氏)
レビューをはじめとした積極的な情報提供が重要に
「モノを見るのはオフライン、買うのはオンライン」という購買行動が広がってくると、それに合わせた新たな店頭マーケティングが求められるようになる。そこでは「ECの果たす役割がより重要になる」と山崎氏は続ける。
「消費者は店頭でもスマートフォンを見てさまざまな情報を収集することが、今は当たり前になっています。それを止めることは現実的に不可能でしょう。では、どうすればよいかというと、積極的にその情報収集に協力するしかありません」
具体的には、まず自社ECサイトで商品の性能や成分などのスペック詳細、価格推移、レビューなどの各種情報を充実させること。そして、店頭で顧客がそれらの情報をすぐ見られるように、タブレットを常設して表示したり、顧客のスマートフォンから容易にアクセスできるようにQRコードを用意したりといったことが考えられるだろう。
提供すべき情報の中でも特に重要なものとして、山崎氏は「レビュー」を挙げた。山崎氏が紹介した米国のリサーチ会社のレポートによると、ECサイトのレビューが1つもない商品に1件レビューがつくとCVRが10%増加し、10件になるとCVRは1.5倍に、50件になると2倍になるという結果が出ている。さらに、4点のレビューが20件あるよりも、3.5点のレビューが100件あるほうがより多くの売上を上げるという、レビュー母数の重要性を示す統計データもあった。

「時には耳の痛い批判的なレビューを書かれる可能性もありますが、それらも受け入れて積極的に取り入れていく必要があります。OMO時代においては、レビュー情報が外部でしか入手できないという状況は大きな機会損失につながり、自社のサイト・店舗の顧客をみすみす流出させてしまうことにもなりかねません」(山崎氏)
レビューの増加によって返品率を抑える効果も
国内トップクラスの導入実績を誇る商品検索エンジン「ZETA SEARCH」を擁するZETAでも、3年前よりレビューエンジンの「ZETA VOICE」を提供している。「実は発売から去年まではあまり売れていなかった」という山崎氏だが、レビューの有効性を示す実証データなどが広く認知されるようになったこともあり、最近は導入企業数もかなり増えているそうだ。
Markezineの記事でも導入事例が紹介されているが、ZETA VOICEを導入したファッション通販サイト「サンエービーディーオンラインストア(SANEI bd ONLINE)」では、目標の半分の期間で3,000件のレビュー獲得を達成。レビューが投稿されてCVRが180~250%に向上した商品もあり、返品率が減少する効果も期待されている。
「レビューが増えることによって返品率が減るのは、『イチかバチかの賭け』のような買物を減らせるから、つまり、顧客がレビューを読み込むことによって納得したうえで購入できるようになるからです」(山崎氏)
まずは商品との出会いを 認知のため「検索」に注力すべき
OMOに対応するうえでは、レビューとともに「検索」も重要な要素となる。
「商品選択のステップは、その商品があることを知る『認知』と、その商品に対する『共感』に分けられます。レビューは主に共感の部分を担いますが、その対象となるべき商品を見つけられなければ始まりません。そこで認知のために不可欠なのが検索です。そもそも顧客が気に入る商品に出会えるようにすることは、コマース事業の基本中の基本ともいえますで、そこはぜひ注力していただきたいと思います」(山崎氏)
なお、ZETAの商品検索エンジン「ZETA SEARCH」は、2017年時点の調査で国内EC企業の売上高上位100社のうち25%に導入されている(山崎氏によれば、現在は30%以上とのこと)。導入後の継続率も98%と高く、他社製品への乗り換えは発売から12年間で1件も発生していないという。

「実績には自信を持っていますが、残念ながら知名度があまりないことも認識しています。そこは完全に当社の責任なので、こうした場でもっと積極的に情報を発信してがんばらなければいけないと思っています」(山崎氏)
その一環としてZETAでは、11月にポルトガルのリスボンで開催される世界最大級のテクノロジーカンファレンス「Web Summit」へ日本企業としては初となる大型協賛を決定。さらに、同カンファレンスのCorporate Innovation Summit(CIS)ステージに山崎氏がスピーカーとして登壇し、日本企業の成長をテーマに講演するという。
「お気軽にというわけにはいきませんが……興味のある方はぜひお越しください。また、OMOに取り組みたい、検索を改善したい、レビュー機能を導入したいなど、検討されている方はお気軽にご相談いただければと思います」と山崎氏は語り、セッションを結んだ。