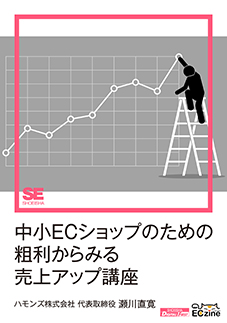コミュニケーションでできることの境界を広げるSlack
Slackはチャットとして知られていると思いますが、「Slack Frontiers 2019」に参加してチャット、さらにはコミュニケーションの枠をさらに超えた大きな潜在性を感じました。
イベントは4月25日と26日の2日間、開催されたのは本社のあるサンフランシスコですが、イベント会場として有名なモスコーニセンターでも、ホテルのイベントスペースでもなく、Pier 27とPier 29。Pier 27にはレジストレーションと展示会場、セミナースペースがあり、Pier 29は基調講演とセミナー会場。1,700人の来場者はその間をいったりきたりすることになります。幸い天気が良く、その間にあるオープンスペースでランチを食べたり、ジュースを飲んだりする姿が見られ、ずっと閉じ込められるイベントと比べると気持ちが明るくなります。行き交う人たちの顔も心なしか笑顔で、声を掛け合うような開放的な雰囲気が漂いました。会場の演出は重要だと感じます。なお、1,700人という参加者数は、昨年の2倍以上だそうです。
イベント名の“Frontier(フロンティア)”は未開拓領域や最先端を表す言葉。Slackは電子メールからの脱却を呼びかけており、新しいコミュニケーション、コラボレーションのツールとして、さらには組織や働きかたを変えるものとしてSlackを位置づけています。Slackユーザーのフロンティア精神を讃えてのネーミングと言えるでしょう。
Slackはこのイベントの後にIPOを行いますが、Frontiers中はIPO直前とあって、売上などの数字には触れず。一方で、同社が目指す“ビジネスコラボレーションハブ”をしっかり訴求する発表を行いました。たとえばSlackを使っていない人と、自分はSlackを使い、相手は電子メールを使いながらやり取りができる(相手にSlackへの招待を送っていることが条件)機能、社外の組織などとチャンネルを共有できる機能などが発表されました。
いくつかの発表の中でも注目すべきは、ワークフロービルダーという自動化作成機能です。チームに新しいメンバーが入るなどのトリガーに対してアクションを設定しておくことで、繰り返しの多い作業を自動化できます。コードを書くことなく、フローに従って設定できるので開発者にお願いする必要はありません。Slack社内でも人事で利用しているようですが、マーケティングや営業でも活用できそうです。この機能からは、Slackが単なるメッセージやコラボレーションの枠を超えた機能に取り組んでいることがうかがえました。
Slack Frontiersでは企業がどのようにSlackを使っているのかの事例も多数紹介していました。Oracleでは14万人が使っているそうですが、“Oracleを再びクールな会社にしよう”という取り組みの中でSlackを選んだという点がとてもおもしろく感じました。ITツールはそれだけで仕事を楽にしてくれるものにも、面倒にしてくれるものにもなり得えますが、コミュニケーションやコラボレーションにはとくに影響が強く、Oracle幹部の「Slack導入により企業の文化が変わってきた」という感想は印象的でした。

迫力のある姿と堂々とした話しっぷりでチームやリーダーシップについて語りました。
右はSlackの共同創業者兼CEOのStewart Butterfield氏。
そのSlackですが、実はゲーム開発をしている時に、地理的に分散したチームが簡単にやり取りできるためのツールとして開発されたという経緯があります。ゲームは鳴かず飛ばずでしたが、副産物のSlackはいけるのでは?──現在CEOとして同社を率いるStewart Butterfield氏は、写真共有サービスFlickrを立ち上げた人物でもあり、この辺りの目の付け所はさすがと言えます。そのSlackは現在、150ヵ国で使われており、デイリーアクティブユーザーは1,000万人とのことです(イベント時)。6月20日にIPOを行い、これから本格的にエンタープライズへの進出を強めると見られます。