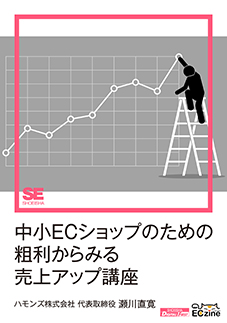B2B企業 vs B2C企業のカスタマーエクスペリエンスに対する取り組み
オープニングセッションは、「B2B企業 vs B2C企業のカスタマーエクスペリエンスに対する取り組み」をテーマにパネルディスカッションが行われた。B2B企業からは横河電機 阿部剛士氏が、B2C企業からはベイシア 竹永靖氏が登壇、SAPジャパン 高山勇喜氏がモデレーターを務めた。
ベイシアグループは、スーパーマーケットのベイシアやホームセンターのカインズ、作業服を扱うワークマンなどを展開しており、グループ全体で約2,000店舗、年間8,000億円の売上高を誇る小売業である。グループのITに関する業務を一手に担うのが、竹永氏が所属するベイシア流通技術研究所だ。B2C企業の代表として登壇した、ベイシア流のあるべきカスタマーエクスペリエンスとは。

株式会社ベイシア ベイシア流通技術研究所 Web開発部 部長 兼 海外Eコマース担当 竹永靖氏
「ホームセンターのカインズでは、日用雑貨を買いに来られる主婦の方たちの割合がもっとも多く、週2~3回という高頻度で来店されています。一方で、農業資材や工業資材をお仕事で購入されるB2Bのお客様もいらっしゃいます。当社ではお客様を数十種のパターンに分類できると分析仮説し、それぞれのお客様にあったタッチポイントで、カインズにしかできないエモーショナルな体験をしていただきたいと考えています。
B2Cのお客様にとってのあるべきカスタマーエクスペリエンスとは、日用雑貨のお買い物であれば定期購入モデルであるとか、購入した材料で作ったお料理やDIYをSNSでアップされたい方には『場』を提供するであるとか、収納用品やインテリアを探しに来られる方にはお部屋にあうものをARやVRを駆使してオススメするといったことが考えられます。
B2Bのお客様は『今日の仕事にこれが必要だ』というものを求めて来店されるため、カインズの1万平方メートル以上の広い店舗、10万SKUの中から、ご所望のネジをすぐに見つけて差し上げなければならない。それがベテランのスタッフでなくてもできるよう、AIを活用するなどしてサポートしていく必要があると考えています」
横河電機は、プラントの生産設備の制御・運転監視を行う制御分野のリーディングカンパニーとして知られ、計測機器や航空関連機器なども提供する。2017年度の売上高は4,066億円、社員の6割が日本以外の国籍を持つグローバル企業だ。阿部氏は同社に約2年前に入社、マーケティング本部長を務める。

横河電機株式会社 マーケティング本部 常務執行役員 マーケティング本部長 阿部剛士氏
「売上の9割をプロセス・オートメーション事業が占めていることに危機感を感じ、変革を起こそうとしています。その一環としてカスタマーの定義も変更し、従来の発注者から、『社内・外、直接的間接的にかかわらず、お互いに影響を及ぼし合って新しい価値を創造できる対象』としています。これに当てはまるのであれば、たとえば人間に限定せず、動物だって顧客になりえます。
この定義のもと、あるべきカスタマーエクスペリエンスを考えると、重要なポイントである『購買』の意味が変わってきています。B2Cほどではないかもしれませんが、B2Bであっても『購買』が『自己表現』になってきている。たとえば、横河電機のプラントを購入することによって、CO2を何%削減できるから選ぶといったことです。当社としては、クライアントにどのような自己表現をしていただくかを製品の開発に取り入れ、カスタマーエクスペリエンスを考えるようにしています。
とくに注力したい分野として、農業や漁業のような第一次産業を将来第六次産業に昇格したいと考えています。俗に3Kと言われるこの分野を、ICTなどのテクノロジーを使うことによって、農業をやりたい、漁業をやりたい人が増えるようにしていきたいのです」
先進企業であっても、あるべきカスタマーエクスペリエンスに向かって、一歩ずつ歩を進めているのが現状だ。その中途のステップについて、詳しく述べてほしいと高山氏は水を向けた。
「課題のひとつに、お客様のことをよく理解できていないということがあります。今でこそカメラやセンサーのようなテクノロジーが出てきていますが、これまでは実際に来店し、購入していただかないとデータが取得できませんでした。また、販促には新聞の折込チラシなどに莫大な金額を投資していますし、現時点でもやめると売上に影響します。こういったレガシーな状態から、デジタルトランスフォーメーションを起こしていかなくてはなりません。システム的には、AsIsで継ぎ接ぎしてスパゲティ状態になってしまっているものを一度壊して、ToBeの視点からどうするべきかを考え、外部の力を借りながら取り組んでいます。
先程、お客様を数十種類に分類できるかもしれないと分析したと述べましたが、その分析を外部コンサルティング会社の力を借りずに自社内で行っています。なぜなら、災害がありそうだからブルーシートが売れる、実はネジと発泡酒がセットで売れているといったノウハウを持っているのは、店舗のスタッフだからです。このノウハウを活かすためにも、さらなるデジタル化を進めていかなくてはと考えています」(ベイシア・竹永氏)
「100年の歴史を持つ企業ですから、埋めなくてはいけないギャップばかりですが、代表的な3つをあげると、ビジネスモデル、デジタルトランスフォーメーション、マーケティングです。
ビジネスモデルについては、お客様が変化していることが大きいです。従来は、お客様自身が5年先、10年先はこうなるであろうというシナリオをプランニングし、サプライヤーはそれを実現するためのモノを提供していました。しかし先が読めない時代になり、シナリオが描けなくなっている。お客様から、シナリオの提案を求められています。ほかにも、B2Bは対面営業が大好きでしたが、事業を拡大するほど回りきれなくなりEコマースをやる必要が出てきた。その都度の販売でなく、サブスクリプションも求められています。
デジタルトランスフォーメーションは、どの企業にも共通する課題だと思いますから説明を省き、3つめのマーケティングについて話したいと思います。基本的に日本の会社は、いいものを作れば売れた時代が長いので、マーケティング部門の地位が低いし、やりかたを知らない。B2B企業ではなおさらです。そんな状況下で私は2年前に横河電機をマーケティング企業にするために入社したわけですが、従来のマーコムやブランディングといった典型的なマーケティング部門だけではなく、横河電機としての新規中期・長期事業計画立案、R&D部門や新事業開発、M&A、アライアンス部門、さらには特許室、戦略的世界標準、工業デザイン室などを配下に置いてもらいました。なぜなら、私にしてはこれらすべてマーケティング資産で、そうしなければVUCAワールド時代の変化のスピードに追いつけないからです。クライアントに製品やサービスなどのプレゼン資料だけでなく、横河電機としてのビッグ・ピクチャーやそのアイディアを具現化したもの(PoC)を作り、実際に具現化して示さなければ話にならなくなってきた。私のような外部から来た人間も役員にし、組織も変えて、会社を変えていく。そこまでしなくては、数年後に横河電機はないかもしれないという、代表の考えによるものです」(横河電機・阿部氏)

両者からデジタルトランスフォーメーションというトピックスが出たこともあり、B2B、B2C問わず共通する課題があるのではないかと、高山氏はふたりに意見を求めた。
「阿部さんのお話を聞いていて、つくづくトップダウンが重要であること、そして日本人が苦手なPoCをどれだけ早く回せるかだと感じました。当グループが地域のお客様に支えられて売上8,000億円まで成長したのも、ものすごい安全経営だったからであり、視点を変えるとあまり冒険してこなかったからです。しかし、ライバルは日本のホームセンターだけではなくなっている。トップ自らが海外視察に行くことで、たとえばロボットがスーパーの在庫品出しを検知しているのを見て衝撃を受け、早期にデジタルトランスフォーメーションを行っていかなくてはならないと動くようになりました。もっと一生懸命デジタルを活用しないと、海外ベンダーから見て日本市場のために自社のソリューションをローカライズする必要がどこまであるのかと思われてしまう。するとシステム的にも遅れをとり、海外のライバルに太刀打ちできなくなってしまいます」(ベイシア・竹永氏)
「竹永さんのおっしゃるとおりで、B2B,B2Cの共通の課題として、ITを使いこなさなくてはいけないというのがあります。それも、守りでなく攻めのITです。日本の場合、個人の生産性や効率を上げるといった視点で投資しがちですが、欧米企業の場合はITを使ってどういう価値を生むか、ビジネスモデルを変革するかの視点で投資します。顧客満足がよく言われますが、満足させて50点、あとの50点はどういう価値を提供するかです。そのためにはリスクをとらないといけないし、そういうITの使いかたに変えていかないといけないと思います」(横河電機・阿部氏)

SAP Customer Experience ソリューション事業本部 事業本部長 高山勇喜氏
このパネルディスカッションの内容を受け、モデレーターを務めたSAPジャパンの高山氏が、7月25日に発表した、CRMを刷新する新しいアプリケーションスイート、SAP C/4HANAの詳細を解説する「全てのボトルネックを排除し、最良の顧客体験を実現するC/4HANAのご紹介」と題し、講演を行った。
Pioneer DJ社導入事例
GDPR対応とLTV向上を両立する顧客ID/データ統合
「GDPR対応とLTV向上を両立する顧客ID/データ統合」セッションにはまず、NTTコム オンライン・マーケティング・ ソリューションの嶋田貴夫氏が登壇。
グローバルビジネスを展開する企業を中心に導入が進む、顧客ID情報の統合・活用の基盤「カスタマー・アイデンティティ・マネジメント(CIM)」。SAPでは、その代表的なソリューション「GIGYA」を2017年9月に買収し、「SAP Customer Data Cloud from Gigya」として提供している。NTTコム オンラインでは、SAPの買収以前から、日本でGIGYAを提供してきた。

NTTコム オンライン・マーケティング・ ソリューション株式会社
CIMエバンジェリスト 嶋田貴夫氏
まず嶋田氏は、日本ではあまり馴染みのないCIMについて解説。
「多くの企業が、実店舗、EC、カタログサイトなどチャネルごとに別々の顧客データを持っています。オムニチャネルでキモになるのは、このデータを統合し、そのデータを活用することで、どのチャネルにおいても個々のお客様に同じ体験を提供することです。
しかし、バラバラになっている顧客データを統合するソリューションがなく、オムニチャネルはもちろん、マーケティングオートメーションやプライベートDMPの活用においても課題となっていました。こうした背景から、急速に立ち上がってきたのがCIMです。2019年に市場規模2兆円を超えると予測され、それはマーケティングオートメーション市場の3倍にもなります。この分野でグローバルナンバーワンの呼声も高いソリューションが、『SAP Customer Data Cloud from Gigya(以下、GIGYA)』なのです」

GIGYAのCIM機能を理解するうえでポイントになるのは、「IDENTITY」「CONSENT」「PROFILE」の3つとなる。
「IDENTITYは、会員登録などログイン周りをすべてカバーするもの。これがあれば、これから新サービスを立ち上げる際に、会員登録機能について悩む必要がなくなります。CONSENTは、GDPRの厳しい基準をクリアするレベルで個人情報管理を行う機能を提供します。そしてPROFILEは、厳重に管理されマーケティングに活用しにくい顧客データを、連携・活用しやすくします」
GIGYAの活用例としては、ユーザーの国籍に合わせたソーシャルログインで会員登録や再ログイン率を向上させた航空会社のサイト、過去に取得した古い顧客データをウェブ上でのアンケートをもとにアップデートした家電サイト、複数のポリシーの異なるサービスをひとつの顧客IDで管理し広告パフォーマンスを上げたメディアサイトなど、さまざまなものがある。
また、SAP Customer Experience (旧SAP Hybris)ほかさまざまなソリューションと開発不要で連携、過去に連携実績がないサービスであってもAPI等の活用で柔軟に連携できるのも特徴である。
このGIGYAを実際に利用し、ID統合プロジェクトを成功させ、LTV向上につなげているのがPioneer DJだ。同社から西川正紀氏が登壇し、講演を行った。

Pioneer DJ株式会社 マーケティング統括グループ CRMグループ マネージャー 西川正紀氏
Pioneer DJは、1994年6月からDJ機器事業を開始。DJ/クラブ機器事業を中核に、業務用音響機器、音楽制作機器、関連サービス事業を展開。ウェブサービスとしては、商品ウェブに加え、DJ向け楽曲管理アプリケーション「rekordbox」、クラブを探したりDJをフォローできる「KUVO」、ソリューションごとのフォーラムと、大きく4つのウェブサービスを展開していた。それぞれが個別のアカウントを発行しており、ユーザーが重複するなど、名寄せができていないことが課題となっていた。
「ユーザーはサービスごとにアカウントを使い分ける必要があるため、ID・パスワードを忘れて離脱してしまったりといったことが起きていました。また、当社からユーザーにメッセージを送る際にも、こちらのサービスのAさんと、あちらのサービスのAさんは同じ人なのかと、判別がつかなくなっていました」
こうした状況を解決すべくコンサルティング会社に相談したところ、GIGYAか自社開発かの選択となり、GIGYAを導入することになった。統合プロジェクトとしては、主となる「Pioneer DJアカウント」を新たに発行。このメインアカウントを利用することで、既存の4つの各サービスいずれにもログインできるようになった。Pioneer DJ視点で見れば、メインアカウント「Pioneer DJアカウント」にすべてのサービスにおける顧客の行動履歴が集約されるため、これだけ分析すればよいという状態が整ったわけだ。
最後に西川氏は、「IDを統合したことで顧客への理解が深められると、『どんなDJが好きなんだろう』といったように、さらに顧客のことを知りたいという欲が出てきました。そして、『このDJが好きな方は、こういったアプローチをすると関心を持ってくれるのではないか』とマーケティングアイディアが浮かんできます。今後はメールシステムやCRMシステムとの連携し、GIGYAをもっと使いこなし、さらに顧客への理解を深めていきたいと思います」と述べ、講演を締めくくった。
カスタマーエクスペリエンスに基づく #グロースハック @TataCLiQ
続いて、2社めのユーザー事例セッションのスピーカーとして、インド最大手のタタ・グループのTataCLiQからSauvik Banerjjee氏が登壇。
TataCLiQは、フィジカル(実店舗)とデジタル(オンラインストア)を組み合わせたオムニチャネルマーケット「フィジタルマーケットプレイス」として展開。現在はインド国内でニューデリーやムンバイなど、100万人以上の顧客にサービスを提供しており、ファッション・家電の分野で160種のブランド、2,000点の商品を扱っている。Banerjjee氏は、自らこのマーケットプレイスを「ユニークだ」と評する。

TataCLiQ CTO Tata Industries VP, Digital Initiatives Sauvik Banerjjee氏
TataCLiQが生まれた背景には、消費者はどのくらい実店舗に行くべきか、どのくらいオンラインストアで購入すべきか、混乱している現状がある。そして、とくに自分たちの強烈なアイデンティティを持つ高級ブランドは、Amazonなどのオンライン上のショッピングプラットフォームで行われる大幅な値引きを良しとはしていない。こうした状況下で、インドで150年の歴史を持つタタ・グループが、オンラインストア業界に参入するに際し、従来のプラットフォームとの大きな差別化ポイントを3つ設けることにした。
「ひとつは、ブランドに特化すること。よく知られたラグジュアリーブランドのほか、ほかのオンラインプラットフォームには出さないけれど、TataCLiQだけには出店しているデザイナーもいます。もしセールを行いたい場合は、ブランド主導で行えるのもTataCLiQの特徴です。
次に、真のオムニチャネル・プラットフォームとすること。フィジカルかつデジタルなプラットフォームを作ることで、消費者はどちらをも頻繁に行き来するようになると考え、実際にそうなっています。TataCLiQでは倉庫を持たず、すべて店舗から配送される仕組みをとっています。裏側には、Uber式のアーキテクチャがあり、オンラインからオーダーが入ると、配送先からもっとも近い店舗がそれを処理することになります。また消費者は、オンライン上で購入した商品の返品・交換を、最寄りの店舗で行うこともできます。
最後に、モバイルに特化すること。現在インドでは、約10億人がスマートフォンを使っていますが、今後は、生まれたときからスマートフォンだけを利用するユーザーが次々と登場してくるためです」
TataCLiQは、ラグジュアリーブランドに特化した「Tata CLiQ Luxury」も運営。35~60歳の消費者をターゲットとしており、高級ブランドの世界観を好み、実際に購入することができる層に特化している。ターゲットを絞ったマーケットプレイスを展開し、そこで一定の成果を上げてから、次のターゲットへのビジネスを展開していこうという考えかたである。
このようにユニークなTata CLiQの「カスタマーエクスペリエンス」の考えかたとは。
「カスタマーエクスペリエンスをどのように計測するのか。NPSや顧客満足度も重要ですが、我々は『カスタマーオブセッション』を指標にしています。具体的には、お客様がオンライン上で商品を見てから、実際に購入し、使用し満足したか、返品・返金になった場合など、計10個のデータポイントがあります。このポイントを、オンライン/オフラインあわせて分析できるのが我々の強みです。
これにより、Tata CLiQは次世代のオンラインストアとしてベンチマークされる存在になっています。10月10日に大きなセールを行いましたが、1日で570都市からオーダーを受け、通常の日の3倍のオーダー数となりました。その日のNPSは50となっています」

続いて、カスタマーエクスペリエンスを語る上で欠かせないパーソナライゼーションについて。TataCLiQでは、SAPなどの協力を得て最先端の取り組みを行っていると言う。
「パーソナライゼーションは、100億のSKUを持つストアにはできないでしょうし、1本のミネラルウォーターのような商品をレコメンドする際には不要です。しかし、TataCLiQのように高級ブランドを扱っている場合には必要になります。我々のレコメンデーションフレームワークは、匿名ユーザーとログインユーザーに分けていますが、ログインユーザーにレコメンデーションを行っています。たとえば、ムンバイに住んでいる男性が、あるブランドの時計についてネットで情報を調べ、TataCLiQに戻ってきた際には、そのブランドのカタログからレコメンデーションを行います。TataCLiQでは、個別のお客様ごとに、たとえば午前9時~12時には何をレコメンデーションするべきかがわかっています。
閲覧履歴、検索履歴、購入履歴からレコメンデーションを行うのはもちろん、ディスカバリーも重要です。たとえば冬の季節には、デリーは寒くても、ムンバイは暖かいということもあります。ムンバイからデリーに出張する人に、ジャケットをレコメンデーションしたらどうでしょう。こういったレコメンデーションを行うには、AIが必要になります。我々は予測、ニューラルネットワーク、天候などのデータも駆使し、何百万というパーソナライゼーションのセグメントを持っています。
検索のパーソナライゼーションも重要です。検索をしている瞬間は、お客様の期待がもっとも頂点に達していますから、その瞬間に最適な結果が出せなければお客様は離脱してしまいます。この件に関しては、SAPやGoogle等と一緒に取り組んでいます」
Banerjjee氏は、TataCLiQのようにリアルタイムにパーソナライゼーションを行う巨大なオンラインストアは、365日24時間休むことができない、まるで株式市場を運営するようだと表現。かかわるシステムも、フロントのECサイトやマーケティングだけでなく、決済や物流など多種多様であり、複雑に絡み合っている。それを支えているのが、SAP Customer Experience、SAP Analytics Cloud、SAP S/4HANAといったシステムであり、今後新たなシステムを追加しても柔軟に対応できるだろうと評価した。
最後に、オムニチャネルの今後と理想形について次のように述べ、講演を締めくくった。
「インドにはたくさんのお祭りやイベントがあり、その際にはブランドの実店舗に長い列ができます。そこで商品を実際に手に取り、注文すると、自宅に届くという取り組みに挑戦しているブランドもあります。消費者は、ネットで日々情報を見ています。その商品について店舗に行く前からよく知っているため、その場ですぐに購入を決めるのです。
このように、お客様がオンラインとオフラインを頻繁に行き来することが、オムニチャネルの理想形ではないでしょうか。我々はそのための機能を多数提供しており、ブランドも積極的に利用し、『フィジタルマーケットプレイス』は好評を得ています。この先2年間をかけて、このプラットフォームをますます拡大していきたいと考えています」
個客を掴む!デジタルマーケティング主導でのビジネスモデル変革

次のセッションでは、レイヤーズ・コンサルティング 佐藤隆太氏が「個客を掴む!デジタルマーケティング主導でのビジネスモデル変革」をテーマに講演。デジタルテクノロジーを駆使して事業全体視点からビジネスモデルをデザインしていく上でのマーケティング&セールス変革のポイントについて、最新の事例や取り組みを紹介した。
マーケティングに革新を起こす、EC推進プロジェクトの勧め
6つめのセッションには、アビームコンサルティング 本間充氏が登壇。まず本間氏は、日本のEC化率について言及。伸びていると言われるEC化率だが、経済産業省の「電子商取引実態調査」によれば、B2C-ECのEC化率については2017年で5.79%。B2C-ECは大きく、旅行や金融等の「サービス系分野」、デジタルコンテンツの「デジタル系分野」、実際のモノの売買である「物販系分野」に分けられているが、物販系はほかふたつと比較して伸びが鈍いのが実態である。
この伸びの鈍さの原因のひとつとして、「企業が考えるECと、顧客が求めるECがマッチしていない」ことがあるのではと、本間氏は指摘する。
それが顕著に現れているのが、Amazonの売れ筋商品だ。トップ10を見れば、実店舗ではあまり見かけない商品が上位を占めている。また、たとえばビールを購入する場合、ECでは箱買い、実店舗ではめずらしい新商品を試してみるなど、場所によって購買行動は異なる。
「これまでオムニチャネルを考える際に、『すべてのチャネルで同じ商品を届けなくては』という発想でいましたが、顧客は、店ごとに品揃えやサービスやコンセプトが違うことを知っていて、使い分けています。企業が考えるECと、顧客が求めるECのギャップはここにあるのです」

アビームコンサルティング株式会社 顧問 本間充氏
こうした状況から、ECは「新しい形態の店舗」であると本間氏。それを意識して「調査・議論・設計」している企業は少ないのではないかと会場に問いかける。
「しっかりとコンセプトが設計されていないから、そのECが何なのか、よくわからない。よくわからないから顧客は利用しないわけです。さらには昨今、顧客は『ECでしかできない体験』を求め始めています」
では、顧客が望むECとはなんなのだろうか。本間氏は、「楽天を好む方とAmazonを好む方がいるように、顧客によって求める理想のEC像は異なる」と言う。そして今や顧客は、従来のマーケティングで用いられていた「年齢」や「性別」といったセグメントで区切ることはできない。わかりやすい例をあげれば、フィギュアスケートの羽生結弦選手のファンには老若男女さまざまいるが、彼らは皆、羽生結弦選手にちなんだ商品には関心を持つのである。
「たとえばGoogleは、検索やウェブの閲覧履歴からそれを知っています。そういったデータを、僕たちは活用すればいいのです」
一方で、デジタルが登場する以前からフィールドワークの顧客観察は行われていたと本間氏。デジタルはあくまで、アナログ時代からあった顧客観察の精度を上げるために使うもの。かつ、顧客がオムニチャネル化しているので、旧来型のアナログな観察だけでは企業側が追いつけないため、デジタルを活用するべきなのだ。
「デジタルで顧客とダイレクトにつながることができるようになった今、直接顧客に尋ねればいいのです。今の顧客は、あるときは消費者だけれど、あるときはビジネスパーソンでもある。自分が好きな企業には、伸びてほしいと思っている。巻き込まれたいのです。先に述べたECサイトの設計においても、社内で議論する以前に、顧客に尋ねてみる必要があります」
ひとことで言えばデジタルとアナログの融合だが、その成功例として、ディノス・セシールが行う「カゴ落ちメール」ならぬ、カートに入れたままサイトを離脱した際の商品のレコメンドがハガキで届く「カゴ落ちDM(実際のハガキ)」を紹介。「カゴ落ちメールが届くと、たいていの場合削除しますよね? それを知っているから、彼らはDMで送るわけです。顧客から見ても、自分にあった情報が届くのはうれしいですよね」
そもそも顧客理解はマーケティングの基本であるが、ECは「IT」の意識が強く、サイトの仕様の話に終始するビジネスの進めかたが蔓延していたと本間氏。それにより顧客がECを求めているものの、ギャップが生まれ、現在のゆるやかすぎるECの成長になっているのではないかと言う。それを変えていくためにも、EC/オムニチャネルの設計においても、まず顧客理解からはじめて欲しいと述べ、講演を締めくくった。
JRキューポを活用したJR九州グループCRM・データマーケティングの実践
最後のセッションには、九州旅客鉄道の相良周平氏が登壇。同社では、社内で別々に運営していた3つのポイントプログラムを「JRキューポ」に統一。そのデータを活用したグループでのCRM・データマーケティングの取り組みについて講演を行った。

九州旅客鉄道株式会社 総合企画本部 経営企画部 グループマーケティング室 室長 相良周平氏
相良氏が講演を終えると、SAPジャパンの高山氏が登壇。最後の挨拶を述べ、イベントは閉幕となった。
【資料ダウンロード】『カスタマージャーニー・ハンドブック
~21世紀のカスタマーエンゲージメント・モデルを構築する方法とは~』
モバイルの普及により、顧客が市場の主導権を握る時代になりました。カスタマージャーニーは予測するのが難しく、同じ経路をたどる旅はひとつとして存在しません。この『カスタマージャーニー・ハンドブック』では、カスタマージャーニーのフェーズを分類し、各フェーズで企業がどういうエンゲージメントに取り組むべきか解説しています。21世紀のカスタマーエンゲージメント・モデルの構築にお役立てください。詳細はこちら