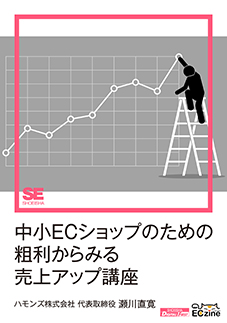看板からもデータ収集を 生き残るため早期からDXに着手
永井氏の父親がLMIグループの前身となるクレストを立ち上げたのは、1987年のこと。「起業したい」と考え、「持続性のあるビジネスは何か」と模索する中、ふと目に留まったのが街中にある看板だった。当時はまだインターネットのない時代。各店舗が通行量の多い駅前や大通り沿いに看板を立てて自社のアピールをしていたが、こうした広告ビジネスは時代が変わってもなくならないだろうと考えたそうだ。
一方、永井氏は大学卒業後、新卒で大手ベンチャーキャピタルに就職。経営悪化した企業の買収から立て直し後の売却までを担当するバイアウト部門にて、事業再生のノウハウを学んだ。そんな中、父親からクレストの事業承継を命じられ、2009年に参画。入社後に経営の実態を把握した永井氏は、こう考えたという。
「創業時に父が掲げた『持続性のあるビジネスをする』という意志を継ぐには、一時的な施策実施ではなく、長期的視点を持った改革が必要と判断しました。
バイアウトを担当していた頃は、『売上の上昇とコストカットによって利益を上げ、結果として企業価値の上昇、売却へと導くこと』が王道とされていましたが、当時のクレストは売却を目的としておらず、会社と社員を守り抜くことが至上命題でした。まだ、デジタルマーケティングやブランディングが今ほどは重視されていない時代でしたが、看板ビジネスだけでは、市場の成長性の観点からどうしても事業拡大が難しくなってしまう。お客様が持つ集客の要望にあらゆる手段で対応できるよう、段階を経た事業アップデートが必要と考え、行動しました」

そこで永井氏は、社員とともに自らテレアポを行い、新規取引先を開拓。小売などとのつながりを作り、既存事業の柱を強固にしながら、店舗へのデジタルサイネージ導入の提案なども開始した。そして、実店舗のデジタル化を進める中で永井氏が気づいたのは、データ取得の重要性だ。
「当時、インターネット上ではアドネットワークが登場し、既にビジネスとして成立していました。ここではユーザーの行動データを当たり前のように収集し、データを活用している。ならば、看板でも同様のことができるようにしなければ、淘汰されてしまうと考えました。リアルな場にいる人々の行動が可視化できれば、企業にとっても大きな財産となる。そう考え、2017年にサイン・ディスプレイの効果検証やAIカメラ活用を始めました」
デジタルの技術を取り入れることでレガシーマーケットからの脱却を目指し、10年以上前進し続けたLMIグループだが、永井氏は事業の拡張を進めながらも「大きな手応えをつかめず、悔しい思いをしてきた」と振り返る。
ところが、コロナ禍やサードパーティCookieに関する規制強化によって状況は一変。リアルとデジタルを融合した施策の重要性が増したことで、近年は日本でも実店舗におけるデータ取得の取り組みが広がりつつある。
「これからの実店舗作りにおいては、来店するユーザーの導線を理解し、最適な広告配置を行うこと、そしてユーザーとのメディアを通じたインタラクティブな接点創出が重要です。データを扱うという意味ではデジタルの知見が活かされる場だと思われがちですが、戦略を描く上では現場視点が欠かせません。ここで、看板屋として当社が長年培ってきた経験やノウハウが役に立つと考えました。
近年、日本でもリテールメディアの考え方が広がり始めています。リテールメディアについては、当社では副社長の望田(竜太氏)が中心となり、新しい価値提供の準備を推進してくれています。望田が参画するまでは、看板屋というレガシーな産業にデータ活用の概念を取り入れ、リアル空間における広告物の効果測定を行うというウェブ上の概念を取り入れた『付加価値』を提供してきましたが、これからは、世の中にまだ深く浸透していない『リテールメディア』という新しい概念の中で、仕組み作りからの『新たな価値提供』ができると考えています。リテールメディアは近々、テレビやウェブ広告と同等の位置に君臨するでしょう。その時に世の中を大きく変革すべく、着々と準備を進めています」